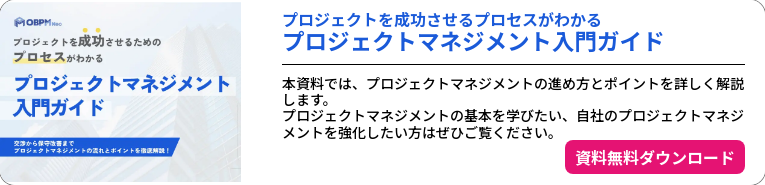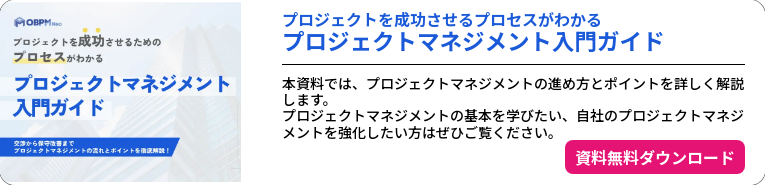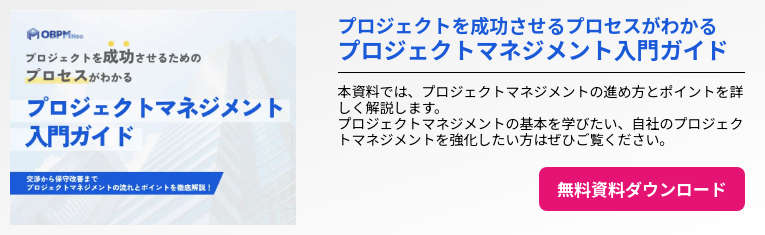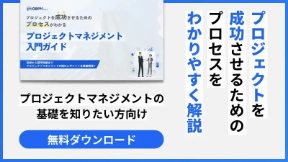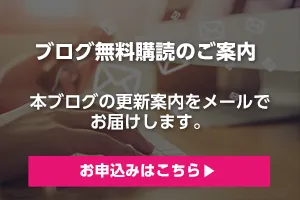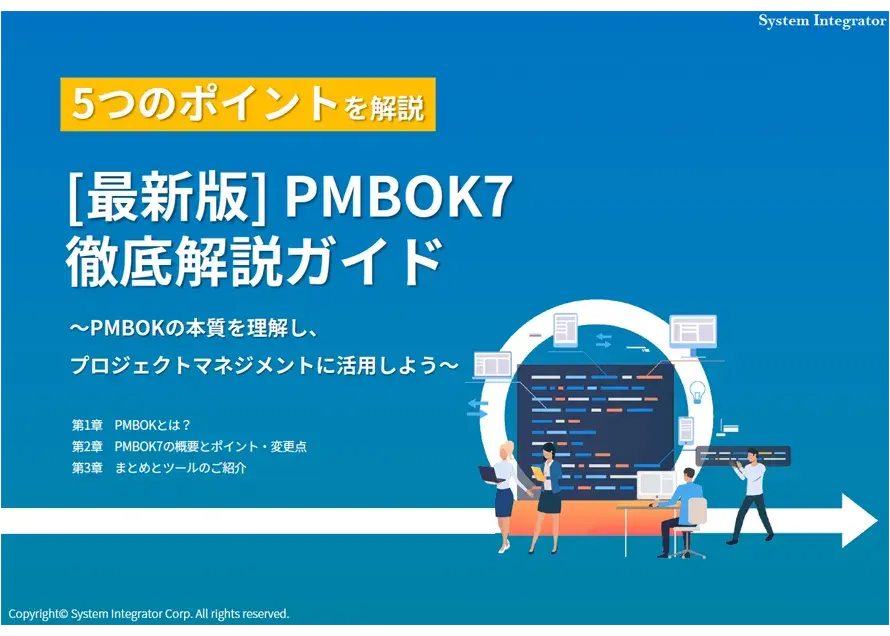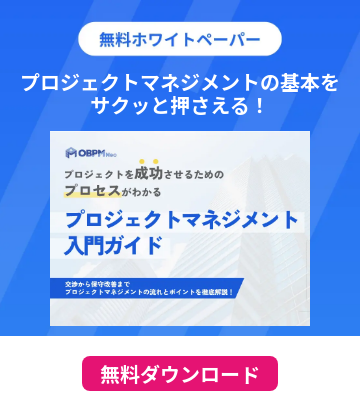業務を遂行する上で、「時間を有効に使い、効率良く仕事をこなす」ことは重要なスキルといえます。ただし、1日24時間という「限られた時間を管理」するのではなく、24時間の中で「どれだけ効率的に業務をこなせるか」に着目することが重要です。ビジネス用語ではこれを「タイムマネジメント」と呼びます。
この記事では、タイムマネジメントの概要と手順、および実行する上でのコツについて解説します。また、タイムマネジメントを行う目的やメリットも紹介します。
タイムマネジメントとは

まずは、タイムマネジメントの定義を解説します。併せて、実行する目的とメリットを見ていきましょう。
タイムマネジメント ≠ 時間管理
タイムマネジメントは直訳すると時間管理となりますが、ビジネスシーンで使用されるタイムマネジメントは時間管理と異なります。「時間を有効に使うことにより、業務生産性を向上させること、または向上を図ること」を意味します。つまり、着目すべきは時間の管理ではなく自身の業務遂行における能力の管理となります。結果として、時間を効率良く使うことにつながるため、タイムマネジメントと呼ばれます。
タイムマネジメントの目的・メリット
タイムマネジメントが求められる理由を端的に述べると、「労働環境の変化」が背景にあります。労働環境の変化とは、「労働人口の減少」と「働き方の多様化」です。
総務省による「令和4年版情報通信白書」の「生産年齢人口の減少」を見てみると、日本国内の生産年齢人口(15歳〜64歳)は、1995年をピークに減少の一途をたどっています。将来的にはさらに減少することが想定されており、労働人口の減少は重大な社会問題といえます。
労働人口の減少は、タイムマネジメントの必要性に直結しています。1人あたりの労働生産性を高めなければ、今まで通りの成果が出せないからです。具体的には、今まで1時間で一つのタスクをこなしていたところを、1時間で二つのタスクをこなす必要があります。
また、働き方の多様化もタイムマネジメントが求められる背景の重要な要素の一つです。例えばテレワークの導入は、代表的な働き方の多様化といえます。最近では週休3日制を導入している企業が増えており、従来の働き方では同様の成果を上げることは困難となっています。異なる環境・限られた時間の中で成果を上げるためには、適切なタイムマネジメントの実施が求められるのです。
タイムマネジメントの実施によって得られるメリットとして、「残業時間の減少」が挙げられます。限られた時間の中で効率良く業務をこなすことは、残業と対極にあるといえるでしょう。残業時間が減ることで、人件費の削減や水道光熱費の節約につながるだけでなく、従業員エンゲージメントの向上による離職率の低下も期待できます。
また、「従業員の能力向上」もタイムマネジメントで期待できるメリットの一つです。短時間でタスクをこなせるようになるだけでなく、重要度の高いタスクと低いタスクの振り分けができるようになるため、個々の従業員の能力向上につながります。
タイムマネジメントの手順
続いて、実際にタイムマネジメントを行う際の手順を解説します。大まかに6つの手順に分けられます。
1.やることを洗い出す
最初に行うべきは、1週間および1か月の業務内容を全て細かく洗い出すことです。単に「事務作業に何分」と大まかものではなく、データ入力作業や書類整理・電話対応など、事務作業に含まれるさまざまな作業を細かに洗い出すことを指します。あらゆる作業の内容とかかる時間・作業の流れを、自分に合った形式で「見える化」していき、自分が普段どのような業務を行っているのか改めてチェックしましょう。「見える化」の形式は自由ですが、追記や修正することを想定してPC上で行うことをおすすめします。
2.工数を確認する
次に、洗い出した作業を実際に1週間や1カ月実施してみて、それぞれの作業にどれくらいの時間を要しているのか確認します。洗い出しの段階で想定していた時間よりも短い作業、長くかかっている作業が明確になり、現実的な工数が判明します。結果に基づき、「見える化」した作業の修正を行うことで、より現実に即したToDoリストが完成するでしょう。
3.優先順位をつける
工数の確認をしたら、各作業の優先順位をつけます。優先順位は、「重要度」と「緊急度」の組み合わせで順位が分かるため、下記のような表で確認してみましょう。
|
緊急性が高い |
緊急性が低い |
|
|
重要度が高い |
①重要度・緊急性が高い |
②重要度が高く、緊急性が低い |
|
重要度が低い |
③緊急性が高く、重要度が低い |
④重要度・緊急性が低い |
「①重要度・緊急性が高い」業務は、時間がかかっても最も優先すべきものです。一方、「④重要度・緊急性が低い」業務は、時間をかけて行っても生産性にはつながらないため、手早く遂行すると良いでしょう。「②重要度が高く、緊急性が低い」業務の場合、①の次に時間をかけるべきものとなります。「③緊急性が高く、重要度が低い」業務では、できる限り迅速に業務を完了させることが重要です。
各業務の「重要度」と「緊急性」を区分することで、どの業務に時間をかけるべきか、どの業務を手早く終わらせるべきかが明確になります。
4.目標を決める
1か月・1週間・1日・1時間と細分化して、明確かつ詳細な目標設定を行いましょう。例として、ライター業の「1か月に30本の記事を納品する」という目標を挙げます。
1日の稼働時間が8時間、1か月のうち20日間が勤務日とすると、1か月に稼働可能な時間は160時間です。1日1本の進捗率では目標の30本には届かないため、記事の納品までにかかる各業務の時間配分を見直す必要があります。
記事の納品までには、以下の業務が必要です。
- クライアントからの受注
- レギュレーションの確認
- 構成の作成
- 執筆
- 校正作業
- 仮納品
- クライアント側の確認と差し戻しの可能性
- 再度作成作業
- 納品
以上の業務と、納品した記事が差し戻される可能性を考えると、1日に3本程度の記事を執筆できれば「1か月に30本」の目標が達成されると想定できます。また、記事作成はチームの協力体制が不可欠なため、執筆作業と校正・納品の担当者を分担するのも方法の一つです。
目標を設定したら確実に達成できるよう、細かいところまで決めておくことが重要といえます。
5.実行
次に、実際の業務を進めてみましょう。1週間・1か月と業務を進めてみて、現実に即した工数設定で問題ないか、優先順位通りの業務遂行で問題ないか、結果として目標は達成できるかを確認します。
6.振り返り
最後は、必ず振り返りの時間を設けます。30分から1時間程度が振り返り時間の目安です。設定したタイムマネジメントに問題はなかったかどうか確認し、なければ現状維持か、より生産性を上げる方向で手順を見直してみましょう。
もしどこかに問題が見つかった場合は、「洗い出し作業に粗があった」「工数確認が現実に即したものではなかった」「優先順位が間違っていた」「目標決めに穴があった」などが考えられます。再度手順を見直し、目標を達成できるよう改善するようにしましょう。
タイムマネジメントのコツ

最後に、タイムマネジメントのコツをいくつかご紹介します。
人に任せる
重要度・緊急性ともに低い業務であれば、必ずしも自分の力のみで行わなくても良いでしょう。手が空いている同僚に業務を任せたり、場合によってはアウトソーシングを活用したりすることも可能です。どれほど詳細にタイムマネジメントを行っても、自分の力だけでは限界があります。自分の能力を超えた業務や、自分が行わなくても良い業務であれば、「他者に任せる」か「業務を引き受けない」ことも、タイムマネジメントを実践する上では大切です。
QCDRSを考える
「QCDRS」とは、「Quality:品質レベル」「Cost:コスト」「Delivery:納期」「Risk:リスク」「Service:配慮」を指す用語です。QCDRSは「成果物」についての概念を指します。
成果物について、以下のポイントを確認する必要があります。
- どれくらいの品質にするか
- どのくらいコストをかけるか
- いつまでに完成させるか
- 完成までに想定されるリスクは何があるか
- リスクに対しどれくらいの配慮を行うべきか
自分で業務遂行までの手順を考える際はもちろんのこと、上司から指示があった場合も必ず確認を取りましょう。指示が曖昧な場合、良質なタイムマネジメントを行うことが困難になります。職場環境や上司との関係性によっては難しい場合もありますが、できる限り「QCDRS」について詳細に確認し、詰めておくと良いでしょう。
時間区切りを意識する
タイムボクシングとも呼ばれる「時間区切り」とは、自分が行う業務について「費やしている時間が不明瞭」な場合や、「より意欲を持ってタスクに取り組みたい」場合に有効な手法です。やり方は、大きなタスクを細分化し、タスクごとそれぞれ数時間に分けて実践する形となります。設定した時間内でタスクを完了させることに集中し、一つのタスクが終わったらまずは休憩を取りましょう。その後、別のタスクを時間内に終わらせることに集中します。このサイクルを繰り返すことが時間区切りです。
タイムブロッキングを利用する
「タイムブロッキング」は時間区切りと似た手法ですが、少し内容が異なります。時間区切りは「タスクの細分化」ですが、タイムブロッキングは「特定の予定をブロックごとにまとめる」手法です。1日の予定で似たような内容の業務をいくつかのブロックに分け、分けたブロックの中で行うタスクを組み込んでいく流れです。タイムブロッキングを利用することで、特定の業務をより集中して取り組めます。
似たタスク・同じタスクをまとめる
成果物が同じタスク・同プロジェクトのタスクなど、業務内容は異なるものの似ている、あるいは同じであるタスクも存在するでしょう。似たような業務に着目せず、タスク単位で仕事をこなすと小さな疲労が積み重なり、やがては生産性の低下につながりかねません。似たタスクや同じタスクはタイムブロッキングの手法を活用して、同じブロック内にまとめましょう。設定したブロックの時間内で似たタスク・同じタスクをこなしていく方がはるかに効率的で、疲労感の蓄積を抑えられます。限られた時間で生産性を向上させるのであれば、非常に効果的な手法です。
1日の終わりに翌日の計画を立てる
出勤してからメールのチェックを行い、その日の予定を慌ただしく組み立てている方もいるかもしれません。業務上、出勤時に行うしかない場面は必ず発生し、緊急のメールが朝に届いていることもあるため、一概に悪いとはいえません。慌ただしい状況でも柔軟に対応できることは、ビジネスにおいて重要です。
しかし、タイムマネジメントの観点からすると、「朝予定を立てる」ことがルーティン化している状況はあまり好ましくありません。できれば1日の終わりに少し時間を設けて、翌日の計画を立てましょう。朝に慌ててしまうことが減り、心の準備ができた状態で翌日を迎えられます。精神的に余裕を持って1日を始められるため、効率良く業務に臨めるようになります。
マルチタスクをやめる
「できる社会人はマルチタスクをこなせる」という考え方は、多くの方に浸透しているかもしれません。確かに複数の業務を同時にこなせる人材は、会社にとって有益です。しかしそれは、「ミスなく全ての業務を完璧にこなせれば」の話です。人間の脳はマルチタスクをしているのではなく、タスクごと瞬時に切り替えて各業務をこなしているだけである、といわれています。つまり、マルチタスクは存在しないという説もあるのです。
業務を効率的に遂行しようとしてマルチタスクまがいの行為を行っていても、脳に疲労が蓄積されていくだけでミスの多発につながり、むしろ非効率である恐れがあります。自身のできる範囲で行う分には問題ありませんが、効率的ではないと感じた場合はマルチタスクをやめて一つの業務に集中して取り組む方が良いでしょう。
休憩を取る
ただひたすらに業務をこなしていても、心身ともに疲れがたまっていき、本来のパフォーマンスを発揮できなくなる恐れがあります。このような事態を防ぐためにも、適宜休憩を取ることは非常に重要です。基本的なことですが、休憩するタイミングを1日の中に組み込んで、不要な疲れをためないようにすることは、業務を効率的にこなすために重要といえます。
まとめ
単なる時間管理ではなく、仕事を効率的にこなすために必要となるのがタイムマネジメントです。タイムマネジメントを行う上で最も重要といえるのが、「優先順位をつけること」と「タスクを明確にすること」の2つになります。これらを適切に実行するためには、プロジェクトにおけるタスクの一元管理、および見える化に取り組むことが重要です。
プロジェクト管理に関する詳しい資料もご用意していますので、ぜひご活用ください。
- カテゴリ: