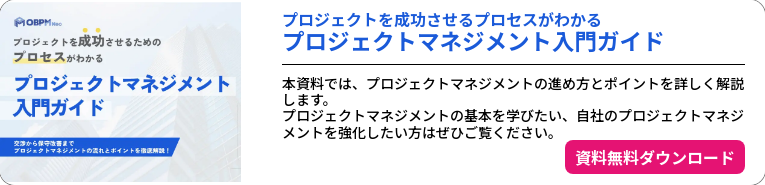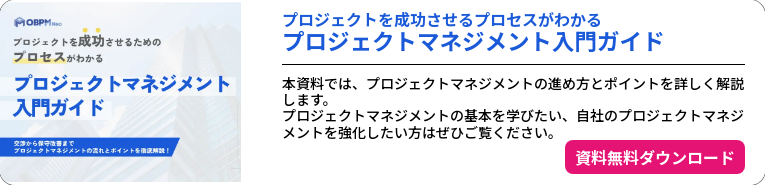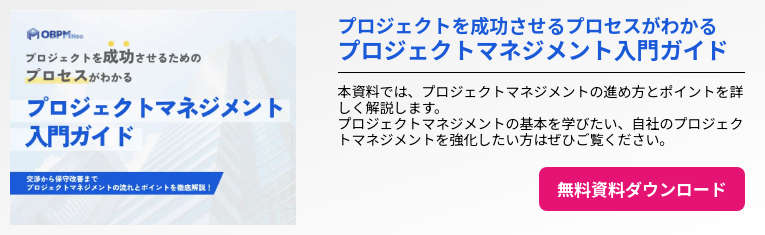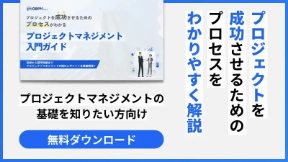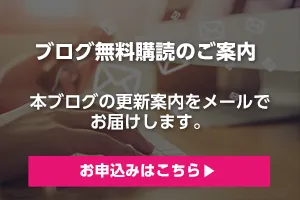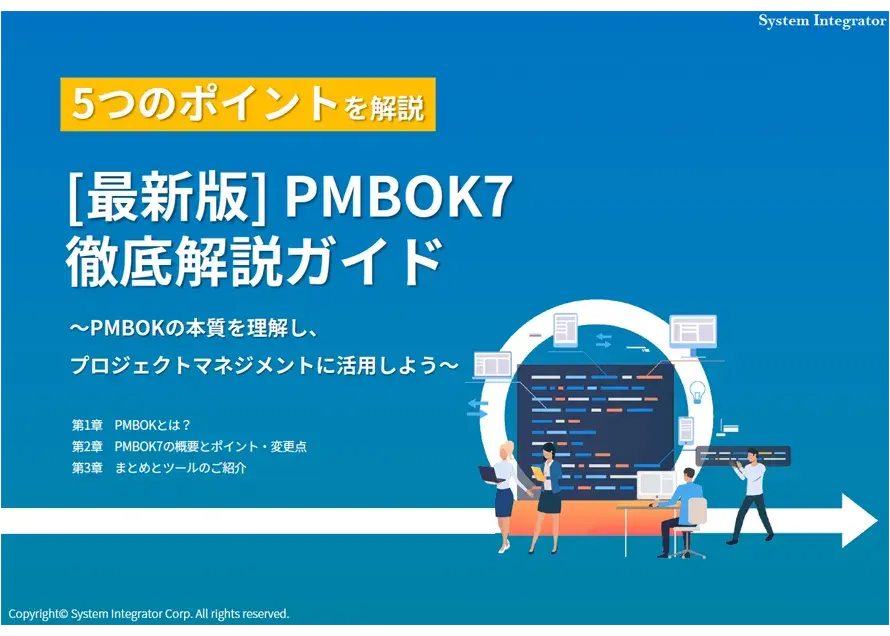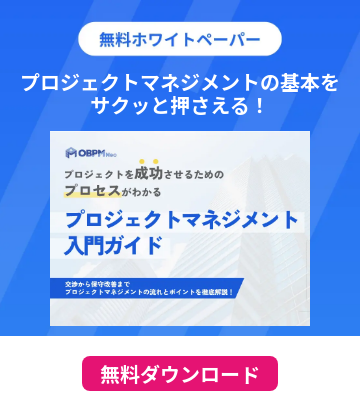ナレッジマネジメントは日本で生まれた経営理論で、企業全体で知識の共有・活用を行い、新しいイノベーションの促進を目指すものです。組織力の強化や業務効率化といったメリットがあります。この記事では、ナレッジマネジメントの手法や導入の流れ、有効なツールについて解説します。
ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントの意味と生まれた理由
「ナレッジマネジメント(Knowledge Management)」とは、個人が持つ知識や経験・スキル、ノウハウを企業全体で共有し、経営に生かす経営手法です。ナレッジマネジメントを行うことで、生産性の向上やイノベーションの促進、円滑なコミュニケーションへとつながります。日本語では知識管理もしくは知識経営と訳しますが、英語の頭文字を取って「KM」と省略されることもあります。
ナレッジマネジメントのメリットは、業務・人材育成の効率化、組織力の向上などが挙げられます。業務知識や仕事のノウハウを従業員が共有できれば、業務や人材育成の効率を上げられるでしょう。また、ナレッジマネジメントによって業務の属人化を防げれば、組織力の強化につながります。
昨今では働く環境の変化や人材の多様化に柔軟に対応していくことが重要です。ナレッジマネジメントは、状況にうまく適応するための手段になり得ることから、企業から注目され、取り入れられています。
いまナレッジマネジメントが必要とされる背景
ナレッジマネジメントが広まった理由のひとつとして、言葉や数字で表しにくいノウハウやスキルの継承に時間がかかっていた背景があります。人材の多様化や雇用形態の変化が進む今のビジネス環境において、時間をかけた人材育成は通用しにくいのが現状です。そこでナレッジマネジメントが必要とされるようになりました。ナレッジマネジメントであれば、企業全体でノウハウやスキルを共有し活用できるため、知識を短期間で分かりやすく継承できます。
ナレッジマネジメントの考え方
ナレッジマネジメントを理解するには、ナレッジマネジメントの考え方を知ることが重要です。ナレッジマネジメントは2種類に分けられる知識タイプと、知識タイプを変換する4つの要素から成り立ちます。ここでは、それぞれの要素について解説します。
形式知と暗黙知
まずは、「形式知」と「暗黙知」の2つの知識タイプを解説します。
・形式知
知識を言葉や図表・数字などで表現したもので、企業ではマニュアルに該当します。知識が言語化されたものであるため、誰にでも理解しやすい点がメリットです。暗黙知を言葉で分かりやすく表したものを、形式知として共有・活用できます。
・暗黙知
言葉や図表などではっきりと表現されない知識やノウハウが暗黙知です。個人が持つスキルや知識・長年の勘など、マニュアル化できないものを指します。言語化が難しい暗黙知は、組織全体で共有しにくい点がデメリットです。
形式知と暗黙知は、ナレッジマネジメントにおける知識の要素で、互いに作用し合っています。暗黙知を形式知に変換できれば、組織内での知識の共有が可能です。ナレッジマネジメントの考え方として、形式知と暗黙知は基本の要素といえます。
SECIモデル
「SECI(セキ)モデル」とは、暗黙知を形式知に変換するプロセスのことです。プロセスはそれぞれ「共同化(Socialization)」「表出化(Externalization)」「連結化(Combination)」「内面化(Internalization)」に分類されます。SECIモデルは、4つの頭文字から取られた名称です。
1.共同化(Socialization)
共同化では、暗黙知の伝達や共感といった作業を進めます。各個人の暗黙知を、同じ体験を通して理解し合うことが目的です。OJT研修や営業先への同行、ロールプレイングなどが該当します。
2.表出化(Externalization)
暗黙知を形式知に変換するのが表出化です。言葉や図表で表される形式知に変換するために、複数人での話し合いを行います。具体的にはミーティングや業務報告、マニュアル作成などです。
3.連結化(Combination)
形式知は単体で機能しないため、形式知同士を連結させる必要があります。連結化は形式知同士を組み合わせるためのプロセスです。連結化によって、新しい知識体系を作り出せます。
4.内面化(Internalization)
内面化は新しい知識体系を形式知として共有し、暗黙知として体系化していくプロセスです。共有や体験によって新しい暗黙知を生み出した後に共同化し、再び暗黙知の共有を進めていく流れを繰り返します。
場
知識の共有や創造の空間・環境として「場」があります。例えば、社内ミーティングやプレゼンテーション、業務の現場などです。その他、オンラインでの会議、電子データベースなども該当します。場はナレッジマネジメントを活用するための基盤ともいえるでしょう。
知識資産
業務の知識や個人が持つノウハウ・人脈といった、企業が活用できる知識を「知識資産」といいます。ナレッジマネジメントでは知識資産の活用が非常に重要です。知識資産にはいくつか種類があり、経験で得たスキルを「経験的知識資産」、マニュアル化された知識を「体系的知識資産」といいます。他にも経営理念といった「概念的知識資産」があります。
ナレッジリーダー
ナレッジマネジメントで成果を出すためには、リーダーシップを発揮し率先して実践できるリーダーが必要です。ナレッジマネジメントに取り組む理由や目的を浸透させ、ナレッジを共有しやすい仕組みを作ることがナレッジリーダーに求められます。
また、ナレッジマネジメントを行う際はツールの使用が基本です。そのため、ナレッジリーダーはツールの使い方も理解しておかなければなりません。
ナレッジマネジメントの手法

ナレッジマネジメントの主な手法は、「経営資本・戦略策定型」「顧客知識共有型」「ベストプラクティス共有型」「専門知識型」の4つです。それぞれの手法を詳しく解説します。
増価×集約:経営資本・戦略策定型
経営資本・戦略策定型は、各個人もしくはチームが持つ知識を分析し、経営戦略に生かす手法です。専用のシステムを利用すれば競合他社の分析が可能で、分析結果によって戦略的な判断ができます。経営資本・戦略策定型を実践することで、業務プロセスの見直しや改善に役立ちます。
増価×連携:顧客知識共有型
顧客知識共有型は、顧客への対応ノウハウやクレーム内容などをデータベース化し共有する手法です。コールセンターや営業・セールスなどでトラブルが発生した際、適切な対応を行うのに役立ちます。顧客知識共有型は、顧客対応の標準化を図ることが可能なため、顧客満足度のさらなる向上を目指せます。
改善×集約:ベストプラクティス共有型
ベストプラクティス共有型は、組織内で優秀と評価される従業員の思考や行動を、形式知化した上でデータベースとして活用する手法です。ベストプラクティス共有型によって、従業員のスキル向上を狙います。例として、優秀な営業社員の商談を録画し、本人の解説付きで勉強会を実施することが挙げられます。勉強会の内容を共有データとして保存し、新人社員に学ばせられるのが特徴です。
改善×連携:専門知識型
専門知識型はネットワークを活用して、組織内外の知識をデータベース化することです。データベース化して検索や閲覧がしやすくなれば、知りたい情報をすぐに手に入れられます。また、組織内で質問が多く集まる項目をFAQ形式にまとめ、見やすくすることも可能です。専門知識型の手法を活用することで、問い合わせが多い部署で発生する対応や業務の負担を軽減でき、応対品質も向上します。
ナレッジマネジメントの導入手順
実際にどのような手順でナレッジマネジメントを導入すべきかを手順をおって解説します。
目的の明確化
まずはナレッジマネジメントの導入目的をはっきりさせましょう。目的を明確化させて組織内で共有することで、従業員のナレッジマネジメントに対する意識が向上します。また、ナレッジマネジメントを実施する目的の他に、企業・従業員が得られるメリットの説明も忘れずに行いましょう。説明の際は目的を理解しやすいように、ナレッジマネジメントを進める背景も含めることが重要です。
共有情報の選定
ナレッジマネジメントの目的が決まったら、次は必要なナレッジ・情報を検討しましょう。業務上の課題をまとめておくことで必要な情報が分かりやすくなります。共有情報を定めておけば、従業員がどのような情報を共有すべきなのか迷いません。
実施方法の決定
次に、ナレッジマネジメントの実施方法を決定しましょう。方法は「エクセル」と「ITシステム」の2つあります。
・エクセルの場合
身近なツールのエクセル(Excel)であれば、導入もスムーズで運用しやすいメリットがあります。ただし、ナレッジの蓄積を目的とする場合は、分析や共有などの情報の活用は難しいかもしれません。
・ITシステムの場合
社内の情報データベースや企業内SNSなどがITシステムです。ナレッジマネジメントで成果を出すための方法は企業によって異なるため、それぞれが適したITシステムを活用する必要があります。
定期的な見直しと改善
ナレッジマネジメントは、ただ運用していくだけでは成果を得られません。効果が出ているか、有効な情報が集まっているかなど定期的な見直しが必要です。確認の際は社内でのアンケート調査を行いましょう。ナレッジ共有の進み具合をチェックし、問題点が見つかった場合は順次改善していきます。
ナレッジマネジメントに有効なツール
ナレッジマネジメントにツールを導入すると、スムーズに知識を集めたりシステムの連携を行ったりすることが可能です。ナレッジマネジメントに有効なツールを5つ紹介します。
グループウェア
グループウェアとは、組織内で情報共有ができるソフトウェアのことです。電子メールやチャット・スケジュール管理・ファイル共有などの機能が備わっています。グループウェアの導入によって、業務の効率化、さらには従業員のスキルアップが見込めるでしょう。
グループウェアは無料で利用できるものもありますが、有料版の方が機能は充実しています。有料版を利用する場合は、ランニングコストがかかる点に注意しましょう。
社内Wikiツール
社内の情報やノウハウをWebブラウザから直接編集できるシステムが社内wikiツールです。社内専用であるため、従業員であれば誰でも記事の作成や追加・更新が行えます。必要に応じて情報を新しくできる点がメリットで、業務の効率化や業務品質の向上といった効果が得られるでしょう。社内wikiツールの利用を活発にするには、ナレッジの共有が重要だと周知する施策を行う必要があります。
AIチャットbot
自動でチャットを行うプログラムのことをチャットbotといいますが、AIチャットbotは人工知能を搭載したチャットbotです。ナレッジマネジメントには、AIチャットbotの活用も有効です。AIチャットbotであれば必要な情報を素早く入手でき、自己解決できる可能性が高まります。また、時間を問わず気軽に利用できる点もメリットです。
CRM
CRM(Customer Relationship Management)とは「顧客関係管理」のことで、営業や商談のデータを統合的に管理するシステムです。CRMには顧客情報だけでなく、商品情報や人脈管理の機能も搭載されています。CRMをナレッジマネジメントに活用することで、営業社員の暗黙知を形式知へと変換できます。
プロジェクト管理ツール
プロジェクトのスケジュールやコスト・メンバーなどを管理するツールが、プロジェクト管理ツールです。基本的な機能にはスケジュールの他、進捗管理表の作成やタスク管理、情報共有などが挙げられます。ナレッジマネジメントにプロジェクト管理ツールを利用すれば、情報をリアルタイムで共有可能です。
まとめ
ナレッジマネジメントを経営に組み込むことで、組織力の強化や業務効率化といったメリットを得られます。多様化するビジネス環境に適応していくためにも、ナレッジマネジメントの活用は企業にとって重要な手段といえるでしょう。
ナレッジマネジメントを導入する際は、グループウェアや社内wikiといったツールを利用しましょう。その中でも弊社が提供しているプロジェクト管理ツール「OBPM Neo」はプロジェクト管理のナレッジが詰まっているツールのため、ナレッジのない新任PMでもPMBOKに沿った管理ができます。OBPM Neoの詳細はこちらをご覧ください。
- カテゴリ:
- キーワード: