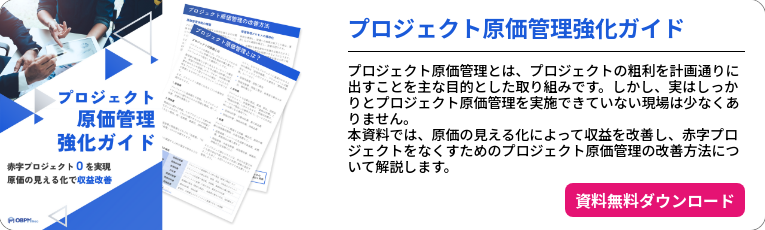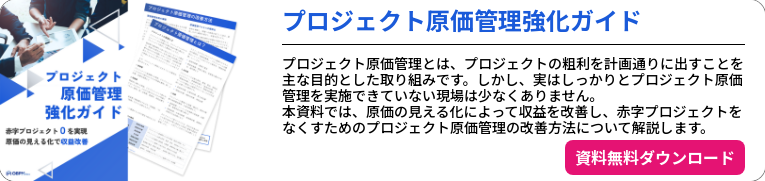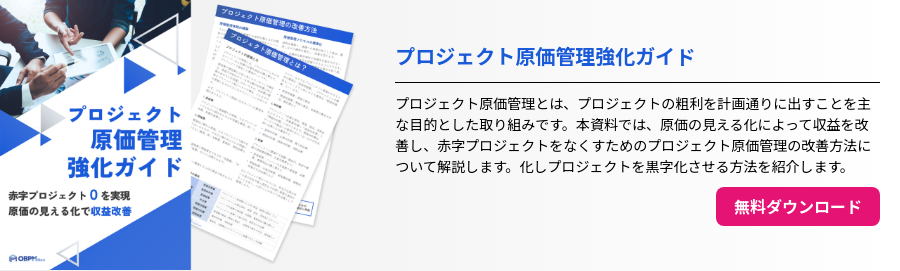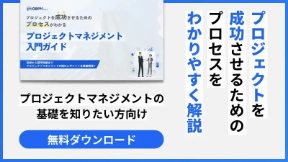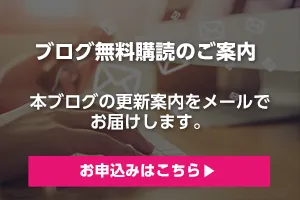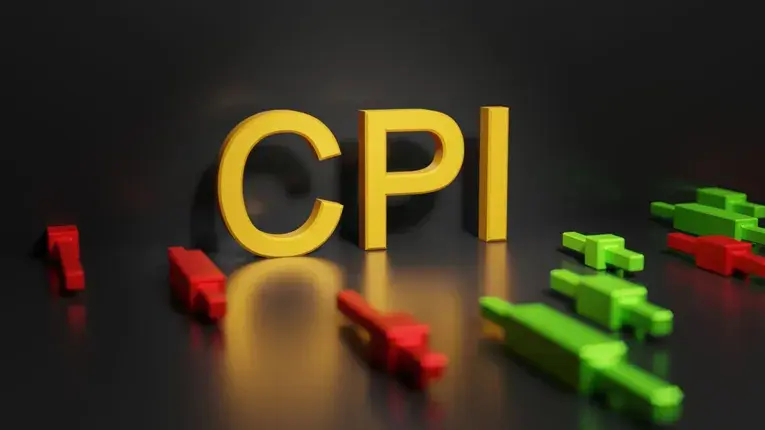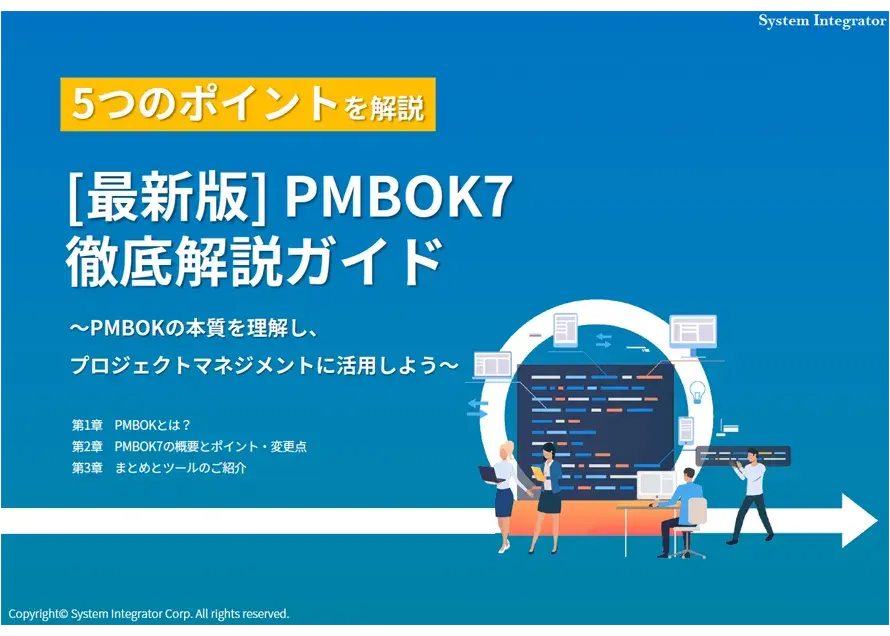原価管理は、赤字化を防ぎ利益率を向上するために欠かせない重要な業務です。しかし、ITプロジェクトなどプロジェクト型のビジネスでは、材料費や工賃など原価構成が比較的シンプルな製造業に比べて、原価を把握しにくい傾向があります。
そこで本記事では、プロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャーに向けて、ITプロジェクトにおける原価管理について原価の基礎から具体的な流れまで詳しく解説します。
原価管理とは
原価管理とは、製品やサービスを作り提供するために必要な材料や設備、人的リソースなどにかかるコストを計画・管理する業務です。予算の計画・立案から工数管理、原価の把握・分析、プロジェクトの改善までを行います。
従来は製造業における製品製造の原価管理が主でしたが、近年はプロジェクト型ビジネスでも重要性が高まっています。特にIT業においてはプロジェクトの大型化・複雑化にともない、プロジェクトの成功率向上のためにも原価管理が重要な役割を果たすようになりました。
原価管理の目的
原価管理の最大な目的は、プロジェクトの原価を抑えて利益を最大化することです。原価管理を適切に行うことで以下のことがより効果的・効率的にできるようになり、プロジェクト成功率の向上、ひいては企業全体の競争力も高まります。
- 予算の遵守
- コストの透明化
- リスク管理
- 意思決定の支援
ITプロジェクトの原価
製造業における「原価」とは、製品価格を構成する仕入・製造・販売にかかった費用を総合した価格です。原価計算基準では「経営において作り出された一定の給付に転嫁される価値であり、その給付にかかわらせて、把握されたものである」と定義されています。
営業利益は原価が低いほど上がり、原価が高いほど下がるため、利益率を上げて企業の競争力を高めるためにも原価低減の取り組みが重要になります。
原価の種類
まず原価には大きく「直接費」と「間接費」の2種類の分類があります。直接費は製品の製造やプロジェクトに直接かかわる費用、間接費は製造やプロジェクトで使われているものの明確に把握できない光熱費や消耗品費などが該当します。また、直接費と間接費はさらにそれぞれ細かく分かれて管理されます。以下は主な費用の分類です。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 固定費 | 売上の増減にかかわらず発生する費用。製造業では作業員の人件費や光熱費など。 |
| 変動費 | 売上の増減に応じて変動する費用。製品製造に必要な原材料や部品の仕入価格など。 |
| 材料費 | 原材料・部品・その他物品にかかる費用。固定的に発生する「固定材料費」と、変動的に発生する「変動材料費」に分かれる。 |
| 労務費 | 従業員の給与や福利厚生、製造やサービス提供にかかる人件費など。社員に関係する「固定労務費」と、パート・アルバイトなど臨時的に雇用する人材にかかわる「変動労務費」に分かれる。 |
| 諸経費 | 材料費と労務費以外のすべての費用。主に設備等にかかった費用。固定的に発生する「固定経費」と、変動的に発生する「変動経費」に分かれる。 |
プロジェクトにおける原価構成
ITプロジェクトにおいては、プロジェクトに直接参画するメンバーの人件費が大半を占めます。原価は以下のように構成されます。
| 直接費 | 直接労務費 | プロジェクトに直接参画するメンバーの人件費など |
|---|---|---|
| 直接材料費 | プロジェクトに必要な資源や消耗品などのコスト | |
| 直接経費 | プロジェクトに直接参画するメンバーの交通費や通信費など | |
| 外注費 | 協力会社に委託する際の外注費 | |
| 間接費 | 間接労務費 | 開発部門メンバーの研修や会議など間接的に計上される人件費や、間接部門の人件費 |
| 間接材料費 | プロジェクトで直接的には使わない補助材料費や消耗品費など | |
| 間接経費 | 各部門で共通に発生する賃貸料や光熱費など |
原価管理の流れ
1.標準原価を設定する
まずはプロジェクトを完了するまでに必要な原価の目標値である「標準原価」を設定します。これがいわゆるプロジェクトの予算です。適正に利益とのバランスがとれるように、過去のプロジェクトデータなどから目安の原価額を概算します。
2.実際原価を計算する
実際原価とは、実際プロジェクトで発生したコストに基づいて算出された原価のことです。
原価計算では、まず一定期間中に各部門で発生した原価要素を労務費や外注費、経費などに分類した「費目別計算」、次に原価部門別に分類した「部門別計算」、最後にプロジェクトごとに原価を集計する「プロジェクト別計算」を行います。
この際、プロジェクトに直接かかわる原価は直接費としてそのまま集計し、賃貸費や光熱費といった間接費は、社員の工数比率や床面積比率などをもとに設定された配賦基準にしたがって各プロジェクトに配賦します。
3.差異分析を行う
差異分析では標準原価と実際原価を比べて、どの費目でどれだけ差分があるか、何が原因でその差分が発生したのかなどを分析し、プロジェクトや事業における課題の発見と改善に役立てます。
差異分析の結果は、不利差異、有利差異、ゼロ差異の3パターンに分けられます。実際原価が標準原価が上回る不利差異となった場合、見積もりの甘さや作業効率の低下、外注費の高騰といった原因が考えられます。逆に実際原価が標準原価を下回る有利差異は、プロジェクトが効率的に進められた状態を示すため問題ないといえますが、あまりに差分が大きい場合は見積もりの精度を見直した方がいいかもしれません。標準原価と実際原価が一致するゼロ差異は、プロジェクトが計画通りに進められたことを示す非常に稀なケースです。
4.原価改善の取り組みを策定・実施する
差異分析で課題が明確になったら、ほかのプロジェクトで同じ問題が起こらないよう改善・再発防止の対策を検討し実施します。
まず分析で明らかになった問題点やコストオーバーの原因を詳細に確認し改善策を立案します。例えば労務費の増加が原因であれば、作業効率を向上させるためのトレーニングやプロセスの見直しを行います。外注費の高騰が原因であれば、外注先の選定基準を再評価し、よりコストパフォーマンスの高い業者の選定を検討します。
改善策の実行段階では、各部門やチームと緊密に連携し具体的なアクションプランを共有します。また、改善策の進捗状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて調整を行います。この際、改善の効果を定量的に評価するための指標やKPIを設定し、達成度を測定しましょう。
最後に、改善の成果をプロジェクト全体に反映させます。成功した改善策は今後のプロジェクトでも活用できるように標準化し、ナレッジとして蓄積します。これにより、ほかのプロジェクトで同様の問題が発生した際にも迅速に対応できるようになります。
原価管理のポイント
原価管理はプロジェクトの成功を左右する重要な要素ですが、その複雑さゆえに、いくつか抑えるべきポイントがあります。以下に、原価管理のポイントを詳しく説明します。
詳細な計画と予算設定
原価管理の第一歩は、詳細な計画と予算設定です。適切な原価管理を行うためには、まずプロジェクトの各フェーズにおける必要なリソースやコストを正確に見積もることが重要になります。過去のプロジェクトデータや業界標準を参考にして現実的な数字を設定しましょう。
見積もりが甘いと、プロジェクトの進行中に予算オーバーが発生するリスクが高まります。予期せぬコストの発生を未然に防ぐためには詳細な計画の立案が重要です。
リアルタイムのコスト監視
原価管理においては、プロジェクト進行中のリアルタイムなコスト監視が不可欠です。タイムリーにコストが把握できるよう常に状況をアップデートし、予算と実際のコストを比較して異常が見つかった場合には即座に対応できるよう体制を整えましょう。問題の早期発見によりリスクが大きくなる前に対策を講じることができるようになり、プロジェクトの健全な進行を維持できます。
なお、リアルタイムにコスト状況を把握するにはチーム全体の協力が必要になるため、工数やコストの状況を報告・共有しやすい体制や仕組みを整える必要もあります。
透明性の確保
コストの透明性を確保するために、どの費用がどこで発生しているのかを明確にすることが重要です。詳細なコスト分類や部門別・プロジェクト別のコスト集計を行うことで、コストの詳細な状況を把握できるようになり、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。また、透明なコスト管理は、ステークホルダーにとって信頼性を高める効果も期待できます。
ツールの活用
原価管理を正確かつ効率的に行うためには、適切なツールの活用が不可欠です。プロジェクト管理ツールや原価管理ツールを利用することで、データの一元管理やリアルタイムのコスト監視が容易になります。ツールの選定にあたっては、プロジェクトの規模や特性など自社の状況にあったものを選びましょう。適切なツールの活用により、原価管理の精度と効率を大幅に向上させることができます。
まとめ
原価管理は一度設定すれば終わりではありません。プロジェクトの進行状況や結果を定期的に評価し、改善点を見つけ出して次回以降のプロジェクトに反映させることが重要です。継続的な改善を通じて、原価管理の精度と効率を高めていきましょう。これにより、プロジェクトの成功率が向上し、企業全体の競争力も高まります。
しかしプロジェクトが大型化・複雑化するなか、従来のように単体の原価管理ツールやExcelで適切に原価管理を実施するのは難しくなっています。
ITプロジェクトにおける原価管理のコツを知りたいという方に向けた資料もご用意しています。こちらもぜひご覧ください。
- カテゴリ:
- キーワード: