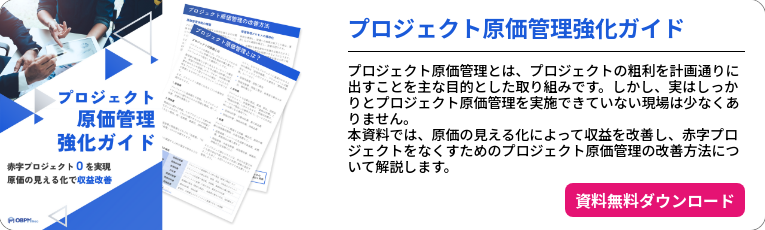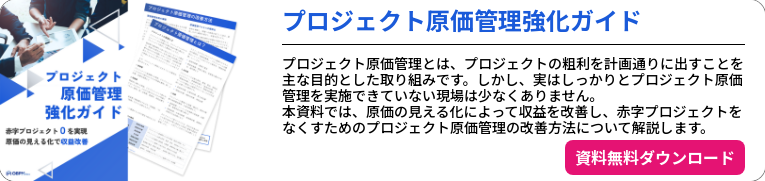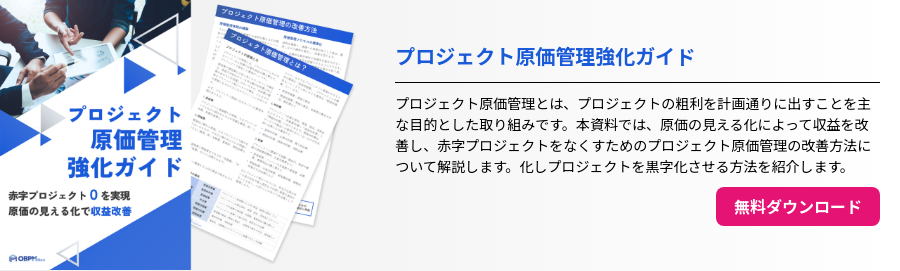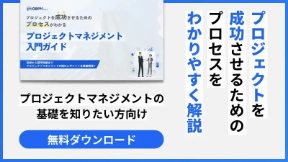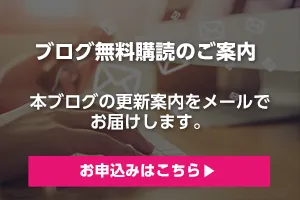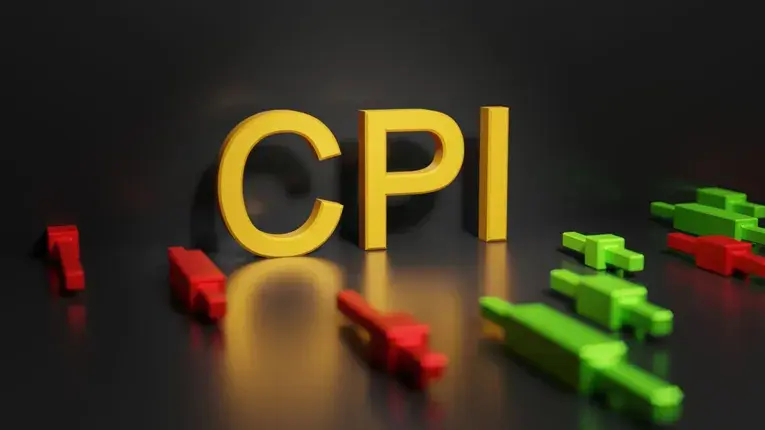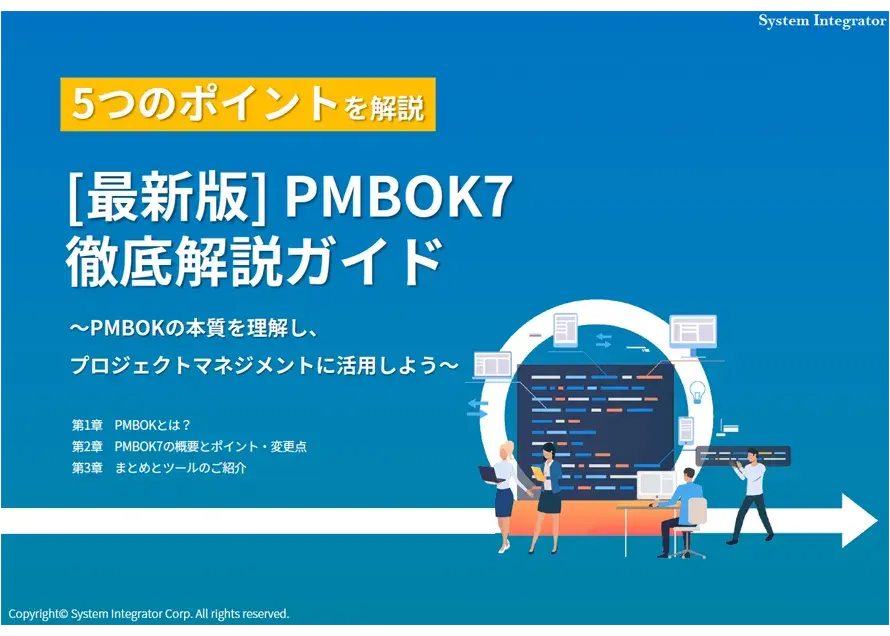事業で利益を生み出すためには、適切な原価管理が重要です。原価管理を行うことで、コスト削減や利益損失リスクの回避、そして経営状態の軌道修正につながります。しかし、「原価管理システムを導入するには、費用や人材が足りるのか」と不安を感じる方もいるでしょう。そこで、原価管理を行う際は、「エクセル」(Excel)の活用がおすすめです。
この記事では、原価管理をエクセルで行う際のメリット・デメリットや、無料で活用できるテンプレートに加えて、エクセルよりも便利な原価管理ツールを紹介します。
原価管理とエクセル
まずは、原価管理の概要を解説します。原価管理の基礎や、エクセルとの関連性を押さえておきましょう。
そもそも原価管理とは
原価管理とは、製品の製造やサービスにかかる原価を管理することです。材料費だけではなく人件費や販売費、設備費など、商品を生み出す過程で必要となったさまざまな費用を原価として把握します。また、原価の計算に加えて、原価を適切に設定できているか分析し、製造過程や原料を見直しながら適切な原価に維持・調整するのも原価管理の役割です。このことから、原価管理は「コストマネジメント」とも呼ばれています。
企業では製造業を中心に、建設業界や広告業界、IT業界などさまざまな業種で導入されています。原価管理を行うことで、原価予測が可能になり、利益改善や損失リスクの回避につながります。
エクセルで原価管理は可能?
エクセルで原価管理することは可能です。エクセルは表計算ツールの中でも多機能であるため、原価管理にエクセルを活用する企業・業種は少なくありません。しかし、エクセルでの原価管理はメリットだけではなくデメリットも存在するため注意が必要です。
原価管理をエクセルで行うメリット
では、原価管理をエクセルで行うメリットを3つ紹介します。取り扱いやすいエクセルを活用して、スムーズな原価管理を行いましょう。
新たにツールを導入する必要がない
エクセルは企業のパソコンに導入されているケースが多いため、新たにツールを導入する必要がありません。2022年3月に行われたキーマンズネットによる利用状況調査では、98.6%の人が勤め先でエクセルを利用していると回答しました。つまり、エクセルを用いれば、ほとんどの企業で原価管理が行えるのです。
もしも新たにツールを導入する場合、ツールの購入費用が必要なだけでなく、マニュアル作成や使用方法に関する研修などのさまざまなコストがかかってしまいます。しかし、エクセルで原価管理を行えば、コストもかからずすぐに運用を始められます。
使い慣れている従業員が多い
表計算ソフトの中でもエクセルは使用する機会が多く、多数の人が操作を経験しています。そのため、改めてツールの使用方法を説明する必要はありません。また、使い慣れている従業員が多ければ、エクセルを使ったことがない人にも使い方をすぐに共有できます。
テンプレートが配布されている
エクセルは普及率が高いツールであることから、さまざまなテンプレートが配布されています。インターネットから無料でダウンロードできるテンプレートが多く、かつ種類も豊富なため、それぞれの企業に合った原価管理表の作成が容易です。また、社内チームで統一したテンプレートを活用すれば、使用方法に迷うことなく原価管理が行えるでしょう。
原価管理をエクセルで行うデメリット
エクセルの導入はメリットだけではありません。続いて、原価管理をエクセルで行うデメリットを紹介します。
属人化が起こりやすい
原価管理にエクセルを用いると、属人化が起こりやすいというデメリットがあります。エクセルは使い慣れている人が多くいる一方、複雑なマクロや関数を扱うためには一定の知識が求められるからです。難しい数式を用いる必要があると、特定の従業員しか原価管理表を扱えない場合もあるかもしれません。その結果、原価の管理業務が属人化してしまう恐れがあるのです。
業務の属人化は、担当者が退職や異動した場合に次の担当者が見つからないなど、組織の柔軟性の低下につながる可能性があります。
最新版のリアルタイム共有が難しい
エクセルでの原価管理は、最新版のリアルタイム共有が難しいという問題があります。作成したデータをパソコンのローカルディスクに保存すると、最新版の原価管理表は作業担当者以外閲覧できません。そのため、最新のデータはメールなどで送信しなければならず、手間がかかってしまいます。
ファイルの管理が手間
原価管理表のデータは、ファイルの管理に手間がかかるデメリットもあります。データを扱う従業員が作業のためにそれぞれのパソコンで保存すると、ファイルが複数ある状態になり業務に影響が出る恐れがあります。最後に更新したデータがどれかわからなくなり、各ファイルを確認する作業が必要になる場合もあるかもしれません。エクセルで原価管理表を扱う際は、担当者間でルールを定めて運用しましょう。
原価管理に利用できるエクセルテンプレート

原価管理しやすいエクセルデータを作るためには、自社に合ったテンプレートを選択しましょう。ここでは、原価管理に利用できるエクセルテンプレートを3つ紹介します。
Microsoftテンプレート「活動ベースのコスト管理」
Microsoftより提供されているテンプレート「活動ベースのコスト管理」では、製品生産に必要な「直接原価」「間接原価」「一般費」「管理費」の管理が可能です。入力したデータから、製品やサービスの価格が決められます。
「活動ベースのコスト管理」は、Microsoftの公式ページより無料でダウンロードできるため、安心して利用可能です。
テンプレートの無料ダウンロードの「原価管理表:Excelで作成」
「原価管理表:Excelで作成」は、一つの製品の原価を計算できます。原価管理表は「原価計算を行う形式」と「チャージレートの計算表」といったフォームが異なる2種類が提供されているため、事業内容に合った原価管理表を選択しましょう。また、自由なカスタマイズが可能なため、どの従業員でも扱いやすい管理表を作成することも可能です。
「原価管理表:Excelで作成」は、Webサイト「テンプレートの無料ダウンロード」の社内向け業務用テンプレートより無料でダウンロードできます。
みんなのexcelテンプレートの「原価売価管理」
Webサイト「みんエク!みんなのExcelテンプレート」では、さまざまな様式の原価売価計算書が提供されています。簡単な計算が可能なシートから項目数が少ない業種に向けたシート、確認印欄が付いているシートなどがあり、社内ニーズに合った計算書を選べます。
こちらは会員登録不要で、原価売価管理カテゴリーから無料でダウンロードできます。
エクセルで原価管理する際のポイント
エクセルの操作経験がある従業員であっても、データを適切に扱わなければエクセルで原価管理できないでしょう。エクセルでの原価管理を成功させるためには、ここで紹介する3つのポイントを押さえておくことが大切です。
無料テンプレートを活用する
エクセルの高度なスキルを持っている人でなければ、原価管理システムを一から作成するには大きな負担がかかるかもしれません。しかし、インターネット上には、エクセルで原価管理をするための無料テンプレートが多数公開されています。導入が不安な企業でも無料であれば活用しやすいでしょう。スキルがある場合でも、ミスを防いだり円滑に業務効率化を実行させたりするのに役立つため、無料テンプレートの使用はおすすめです。
更新のルールやマニュアルを用意する
更新のルールやマニュアルを用意することは、原価管理をする際の重要なポイントです。「管理データが複数あって、どれが最新版かわからない」といった事態を防止できれば、確認作業の手間が省けます。原価管理表のデータの保存先をファイルサーバーの特定のフォルダに設定するなど、データの管理方法を決めておきましょう。ただし、ファイルサーバーやクラウドサービスの利用は情報漏えいなどのリスクも少なからず存在するため、十分なセキュリティ対策が必要です。
また、「専門用語や数値などの解説」や「エクセルで原価管理を行う目的」などが盛り込まれているマニュアルの作成もおすすめです。これにより、新入社員や原価管理業務に携わった経験がない従業員でも理解が深まり、教育に必要な時間をカットできます。
マクロや関数を利用する
データ分析や集計など手動で行わなければならない作業がある場合は、マクロや関数を利用しましょう。手動による表管理は、担当者のスキル・経験によって作業効率が異なってしまうためです。マクロや関数を用いてシステム化すると、スキルに左右されず誰が扱っても安定した結果が出せるようになります。
エクセルよりも原価管理におすすめのツール
エクセルによる原価管理は、運用を始めやすい一方、管理に手間がかかります。一方、原価管理システムを使うことで、原価だけでなく業務全体を効率よく管理できるでしょう。ここでは、エクセルよりも原価管理におすすめのツールを4つ紹介します。
原価管理システム
原価管理システムとは、原価計算や原価の管理、予算の比較、損益の分析などのさまざまな管理を効率的に行うシステムです。シミュレーションによる原価管理を行いやすく、適切に管理できることから、原価低減や利益率の向上に役立ちます。また、エクセルと比べてファイル管理が容易であり、前述したデメリットの1つ「ファイル管理の手間」を省けます。
ツールを扱う際に専門知識は必要なく、数値の入力のみで原価計算できるため、原価管理経験者が不足している場合は導入を検討しましょう。加えて、エクセルでの原価管理に起こり得る属人化や処理時間などが気になる場合でも、原価管理システムの導入はおすすめです。ただし、原価管理システムと関連した他システムとの連携が必要になる場合があります。
会計ソフト
会計ソフトは、原価管理を含めた会計業務全般に対応するツールです。帳簿の自動入力機能があり、会計業務の効率化が期待できます。原価管理機能を実装している会計ソフトを活用すれば、製造原価なども一括で計算が可能です。また、電子マネーや銀行口座などと連携可能な会計ソフトも提供されています。お金の入出金がリアルタイムに反映されるため、迅速な経営判断にも活用できます。
なお、原価管理機能が会計ソフト全てに搭載されているわけではありません。ツール導入の際は、機能の有無を確認しましょう。
ERP
ERPとは、企業が持つ資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を統合管理するシステムです。導入のメリットは、原価管理システムで必要な「他システム一つひとつと連携する作業」に関連する手間・コストを削減できることです。また、多くのERPには企業の資源や組織内情報を一括管理するだけでなく、製造費用や在庫など、原価計算に必要なさまざまな管理機能が搭載されています。ERPの導入は、原価管理のみならず業務の全般的な効率化が実現できます。
さらに、原価管理を一つのシステムで行うことにより、運用コストも抑えられます。
プロジェクト管理ツール
プロジェクト管理ツールとは、原価管理を含め、スケジュールや案件などのさまざまな管理業務を統合できるツールです。タスクの進捗状況が可視化されるため、エクセルによる管理よりも、管理業務の効率化が期待できます。
さまざまなプロジェクト管理ツールの中でも、統合型プロジェクト管理ツール「OBPM Neo」の導入がおすすめです。OBPM Neoでは、プロジェクト進行に必要な「進捗」「採算」「品質」「要員」などを可視化することで、正確な状況把握を支援します。また、工数・原価管理と進捗管理を統合して確認できるため、エクセルやフリーソフトを使うことなく、プロジェクトの正確なマネジメントが可能です。つまり、OBPM Neoは「複数のプロジェクトを効率よく進めたい」「一つひとつの業務の手間を省きたい」といった、管理業務に対する要望にこたえられるツールといえます。
さらに、「OBPM Neoシリーズ」では3つのプランが展開されており、管理したい項目に合わせて選択できます。業務内容に合ったOBPM Neoを検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
原価管理を行う手段として、エクセルを用いた方法が有用です。エクセルによる原価管理は、新たなツールを導入する必要がなく手軽に開始できます。また、無料テンプレートの活用により、システムを一から構築する工程が省けるため、スムーズに運用が始められます。しかし、属人化のリスクやファイル管理の難しさなど、さまざまな問題が生じてしまいます。マニュアルの準備やマクロ・関数の使用などの対策方法はあるものの、手間となってしまうかもしれません。
原価管理は経営判断をする上で重要であり、コスト削減や利益改善につながるため、丁寧な作業が大切です。「原価管理をエクセルで行うのは大変」と感じる場合は、エクセルよりも効率的な管理業務が可能になるプロジェクト管理ツールなどを活用しましょう。
なお、原価管理のポイントをまとめた資料もご用意していますので、こちらもぜひご活用ください。
- カテゴリ:
- キーワード: