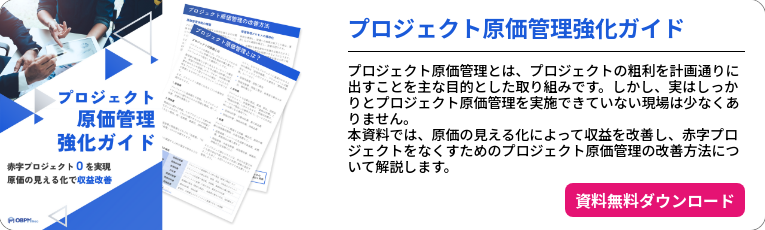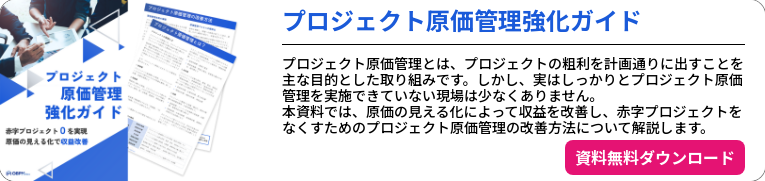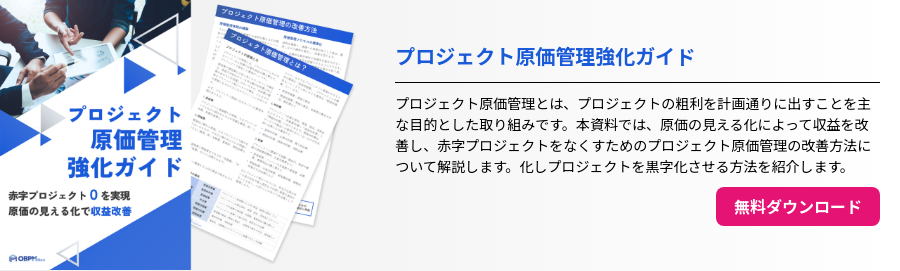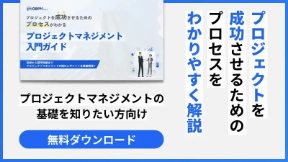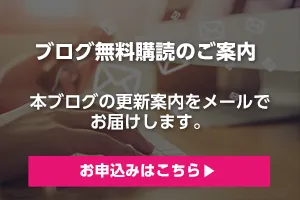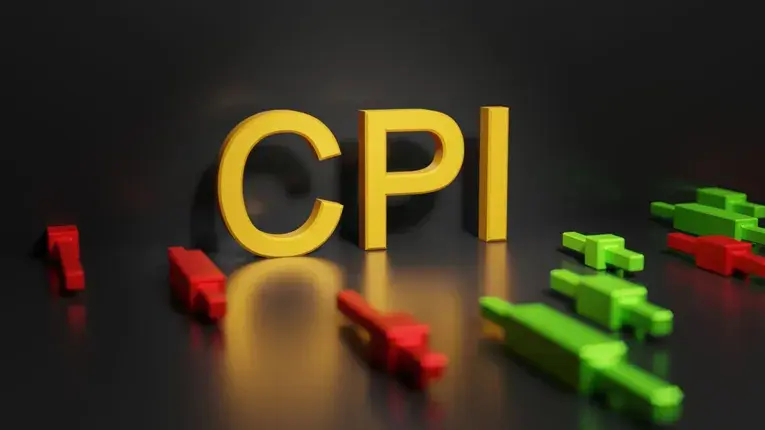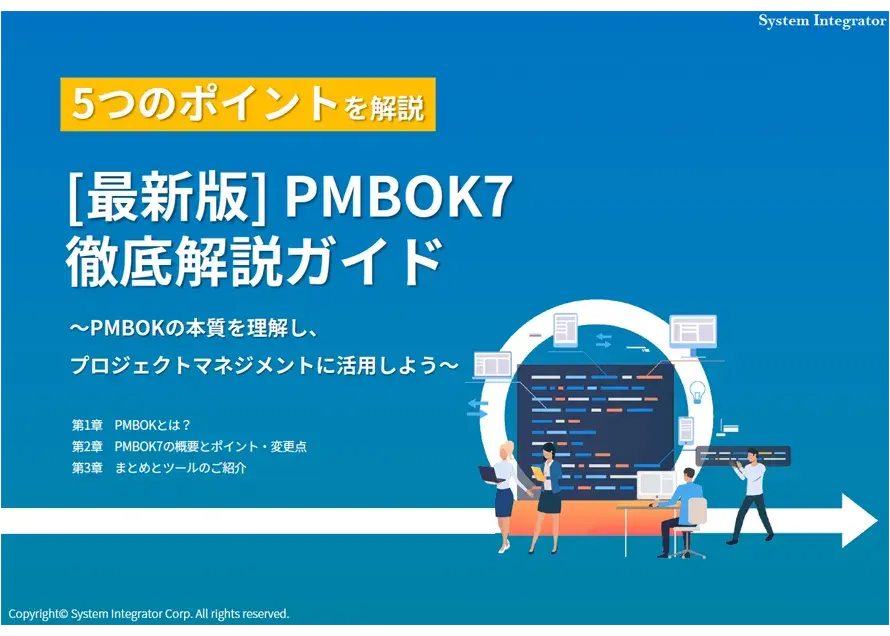製品の製造過程において、材料の調達費用、加工費用、減価償却費用などさまざまな費用が発生します。これら費用を計算して、製造原価を算出するのが「原価計算」です。一般的に、原価計算は企業の経営状態について確認・報告を行う「財務会計」と、生産性や意思決定力を把握するための「管理会計」を目的としています。しかし、原価計算は企業だけが行うものではなく、個人事業主にとっても必要です。
この記事では、複雑な原価計算を行う上で手助けとなる「原価計算アプリ」および「原価管理システム」について紹介します。
原価計算アプリとは
製品の原価を算出するためには複雑な計算が必要です。特に個人で店舗を経営している場合、原価計算に割く手間と時間は他業務の支障となる恐れがあります。そうした手間を省くのに最適なのが、原価計算アプリです。アプリによっては、原価だけでなく利益率や売値まで算出できるアプリもあり、業務効率化が期待できます。
おすすめの原価計算アプリ
まずは、個人向けとしておすすめの原価計算アプリを5つ紹介します。
売上総利益率の計算
このアプリは、原価と売上総利益(粗利)率を入力するだけで売値が自動算出される機能を有しています。そのため、仕入れた商品について自分で売値を決めている「小売業者」の方におすすめのアプリです。
売値を算出するために必要なのは、原価と消費税、そして売上総利益率(または売上総利益値)の入力だけとなります。それぞれを入力することで、売値(消費税込・消費税抜どちらも)が自動算出されるため非常に便利です。一方で、売上総利益率ではなく売値を入力すれば、売上総利益率(および売上総利益値)を算出することも可能です。
また、売値に対して割引率を入力すれば、割引額と割引後の売値も自動算出可能となっており、割引セールを行う際には最適な機能といえるでしょう。
アプリ「売上総利益率の計算」はGoogle Playにて無料でダウンロードできます。iOS版は提供されていません。
レシピ原価計算
飲食店を経営されている方に最適なのが、「レシピ原価計算」アプリです。商品に使う原材料の情報を入力すれば、各商品の売価と原価、および粗利率と原価率が自動で算出されます。原価だけでなく見込み利益も確認できるため、財務会計面における数字の確認にも役立つでしょう。「商品情報」ページでは、商品名と併せてメモも加筆できるため、商品リストとしての機能も期待できます。
原材料の情報は、非常に細かく入力可能です。「仕入単位」「仕入金額」「使用単位」「換算数」「歩留り」に加え、原材料の「分類」「仕入先」「保管場所」「メモ」も追加できます。これらの情報は「原材料入力」ページで入力すると、「原材料情報」ページにて一覧化して確認可能です。
また、商品と個数を選択すれば必要な調達物のリストも作成できます。原材料の数量、仕入にかかる金額、および仕入先まで設定できるので、確認から発注までスムーズに進められるでしょう。
アプリ「レシピ原価計算」はApp Storeにて400円で、Google Playにて350円でダウンロードできます。
シェフのためのFillet原価計算の方策&在庫カウントアプリ
こちらも、飲食関連経営者の方などにおすすめのアプリです。原価計算はもちろんのこと、他にもさまざまな機能を備えています。例えば、「バーコードスキャンによる食材の追加」「既存食材の検索」「食材のグループ化」「最新の米国農務省国立栄養データベースの利用(オフライン利用可能)」などが挙げられます。
また、在庫管理面では「在庫報告書の作成とメール送信」「在庫の追跡(店舗数の制限なし)」といった機能、発注関連では「仕入業者ごとに食材の発注書を作成」「発注書はPDFやCSV形式で出力」といった機能を使用可能です。
さらに、「オフライン使用可能」「複数のiOSデバイス間でデータのバックアップ・同期が可能」「iPhoneとiPad双方に最適化」「サポートフォーラム、ナレッジベース、動画チュートリアルといった補助機能付属」といった機能も付いており、アプリの使用に際しては別途ユーザー登録を行う必要はありません。他にも、fillet.jpを利用すればさまざまなデスクトップやノートPCからアクセス可能です。
アプリ「シェフのためのFillet原価計算の方策&在庫カウントアプリ」は、App StoreやGoogle Playにて無料で配信されています。
ビジネス電卓 - 原価、売価、利益率を計算する
単なる電卓アプリではなく、「損益算」に対応しており見積もり作成が可能です。「原価」「売価」「利益」のうちから2つの数値を選んで入力すれば、残りの値が自動算出されます。それだけでなく、「メモリ演算」「税込・税抜表示」「平方根」「割合(%)計算」にも対応しており、あらゆる計算式について履歴を閲覧できます。
このアプリでは、以下の項目について任意設定ができます。
- 表示モード
100÷3=33.333……(省略表示可能)
100÷3=0.33333E02(指数表示可能) - 小数点以下表示桁数
0~13の桁数で任意設定可能 - 税率
- 端数処理
四捨五入、切り上げおよび切り捨てから設定可能
また、「2種類のキーレイアウトから選択可能」「キータッチ時のバイブレーション機能ON/OFF」「計算画面時スリーブ機能ON/OFF」といった機能も搭載されています。キー操作については、「MRCキー1回押しでメモリから読み込み、2回押しでメモリクリア」「Cキー1回押しで現段階のみクリア、2回押しで全段階クリア」が可能です。
アプリ「ビジネス電卓-原価、売価、利益率を計算する」は、App StoreおよびGoogle Playにて無料で配信されています。
かんたん利益計算
シンプルな機能で利益計算ができるアプリです。入力項目は「販売価格」と「原価」のみ(必要に応じて配送料や手数料も入力)で、「計算する」ボタンを押下すれば利益および利益率を確認できます。この際に用いられる計算式は以下の通りです。
販売価格-「原価+配送料+『販売価格×手数料÷100』」=利益
「利益÷販売価格」×100=利益率
フリマアプリやオークションアプリへの出品、個人販売などのシーンで活用できるアプリといえるでしょう。アプリ「かんたん利益計算」はApp StoreおよびGoogle Playにて無料配信中です。
企業の利用なら原価管理システムがおすすめ

5つの原価計算アプリについて紹介しましたが、いずれも、個人事業主などによる「個人利用」を前提としている面が大きいアプリとなっており、企業が原価計算のために利用する媒体としては少々心もとないかもしれません。そのため、企業レベルの規模感であれば、より複雑な計算や分析が可能となる「原価管理システム」を利用するとよいでしょう。
原価管理システムとは
企業において原価計算を実施する場合、「Excelなどのツールによる処理に限界がある」「実際の数値と差異が生じるなど精度が悪い」といった問題が発生したり、「原価計算のシミュレーションを実施したい」などの要望が発生したりする場合があります。こうした問題解決や業務効率の改善に活用できるのが、原価管理システムです。
原価管理システムを活用すれば、人的コストを削減しつつ、複雑な原価計算や予算と実績の差異分析、原価計算シミュレーションや損益分析ができるようになります。また、生産管理・販売管理・会計システムなどその他のシステムと連携することも可能です。
原価管理システムには、大きく分けて以下4つの機能が備わっています。
原価計算機能
さまざまな費用項目と計算方法を有する原価計算をシステム化することで、精密な数値の算出が可能です。また、コストカットに向けてどの費用項目に対応すべきか把握できます。
原価差異分析機能
分析により、目標原価に対する実際原価との差額が分かります。費用項目単位で分析が可能となるため、「何が問題なのか」がすぐに判断できる、という点はシステム化の大きなメリットといえるでしょう。
損益計算機能
製品・部門別など、さまざまな側面から今期の損益計算書を作成し、来期の予算編成を行う機能です。その際に原価管理システムを活用することで、迅速な予算編成や適切な原価管理が期待できます。
配賦計算機能
製品・部門を横断し、適切な形で配賦が可能です。
法人向け原価管理システムの例
企業における利用を前提とした原価管理システムには、製造業向けや建設業向けといったタイプから、汎用性のあるタイプまでさまざまな種類が存在します。ここでは、その一部として3つの原価管理システムについて紹介します。
マネーフォワード クラウド個別原価
株式会社マネーフォワードが提供している原価管理システム「マネーフォワード クラウド個別原価」は、プロジェクト管理向けタイプの原価管理システムです。プロジェクトの開始から工数入力、個別原価計算、資産振替、レポート作成までの一連業務をワンストップでサポートします。
- 従業員への負荷を減らすことで入力ミスも減らし、正確な工数データの収集が可能
- プロジェクトに関係する全費用項目の収集をデータ連携機能によって迅速化
- 自社運用に合わせた配賦基準を設定可能。配賦比率の自動算出、配賦ルールの変更も簡易化
- 経理担当者の負担なく、クラウド上で最新の原価情報が閲覧可能。参照権限を付与された従業員に正確なデータを提供することも可能
また、「マネーフォワード クラウド」の他サービスとの連携によって、効率的に個別原価管理できます。
楽楽販売
株式会社ラクスが提供している「楽楽販売」は、汎用性の高いクラウド型原価管理システムです。販売管理を中心に、さまざまな業務の標準化・効率化が可能となる、各種業務の一元化を強みとしています。そのため、販売管理にかかっていた月間の費用と時間を削減することが可能です。
主として、以下のような機能を備えています。
- プログラミング開発不要で、Excel取り込みとマウス操作だけでシステム構築可能
- ノンプログラミングで自社仕様にカスタマイズ可能
- リアルタイム情報共有で共有漏れや属人化防止
- ルーチンワークの自動化による業務効率化
- ボタン1つで帳票発行&帳票フォーマットを複数種類登録可能
- 自社稟議規定に合わせた承認フローのシステム化
- 外部システムとの連携可能&充実したセキュリティ機能
OBPM Neo
弊社提供の「OBPM Neo」は、プロジェクトを標準化・見える化させることを目的とした統合型プロジェクト管理ツールです。「脱Excel」を実現し、全プロジェクトがクラウド上のデータベースで一元管理されるため、業務効率の飛躍的な向上が期待できます。原価管理をはじめ、進捗管理や要員管理など、従来のやり方ではExcelで個別に管理されていたデータを統合することで、プロジェクトの全容が把握できます。
法人が原価計算アプリ・原価管理システムを選ぶ際のポイント
最後に、アプリとシステムいずれにおいても選ぶ際に把握しておきたいポイントについて紹介します。
セキュリティ対策は万全か
セキュリティにおいて、「ユーザーごとにアクセス権限が付与できる」「責任者がアクセス履歴を閲覧できる」「データをバックアップサーバーに保管できる」などの対策が適切に講じられていることが重要です。同様に、アプリ・システムを選ぶ上では、問題が発生した際に相談できるユーザーサポート窓口を設置しているかどうかもポイントとなります。
原価計算以外の業務に対応できるか
原価計算・管理だけでなく、その他の管理システムなどと連携可能かどうかも欠かせません。その他システムと連携することで「情報の一元管理」が可能となり、「ERP(基幹系情報システム)」も実現できるようになります。
配賦方法を選択できるか
原価計算・管理を適切に行うためには、自社基準の配賦方法に則したアプリ・システムを選ぶことが重要です。適切なアプリ・システムを導入できれば自動配賦が可能となり、手作業よりも効率的に業務を進められます。
操作しやすいか
「Excel作業からの脱却」による業務効率化を推進している原価計算アプリ・原価管理システムですが、データ分析のためにはExcelを使用する場面も多いのが実情です。そのため、アプリ・システムとExcelとの連携がスムーズで操作しやすいかどうかも、選定ポイントの一つといえます。
まとめ
個人と企業のいずれにおいても、原価計算・原価管理は重要な業務ですが、時間とコストをかけすぎて他業務に支障をきたすのは避けたいものです。そのためには、原価計算アプリや原価管理システムを導入して業務効率化を図るのが最適といえるでしょう。
原価管理のポイントをまとめた資料もご用意していますので、こちらもぜひご活用ください。
- カテゴリ:
- キーワード: