クラウドベースのデータウェアハウスで高い注目を集めているのが「Snowflake」です。Snowflakeは他のデータウェアハウスにはない特長を持ち、データウェアハウスだけでなくデータ共有やAIなど、さまざまな用途で利用されています。
本記事では、Snowflakeの概要および特長を詳しく解説していきます。
Snowflakeとは
Snowflake(スノーフレーク)は、Snowflake社が提供するクラウドベースのデータプラットフォームです。用途としては、データウェアハウスだけでなく、データ共有、データレイク、データアプリケーションの基盤としても活用されています。
最大の特徴は、ストレージとコンピューティングを完全に分離したアーキテクチャです。これにより、ユーザーは必要なときに必要なリソースだけをスケーリングできるため、パフォーマンスの最適化とコスト効率を両立できます。また、SQLベースの操作性やETLツールとの連携も容易で、既存のデータ分析環境にスムーズに統合できる点も評価されています。
Snowflakeの構成
Snowflakeのアーキテクチャは、以下の図のように「クラウドサービス」「クエリ処理(コンピュート)」「データベースストレージ」の3層構造で構成されています。
 【参考】重要な概念およびアーキテクチャ(Snowflake Documentation)
【参考】重要な概念およびアーキテクチャ(Snowflake Documentation)
クラウドサービス
クラウドサービス層では、認証やアクセス管理、クエリの最適化、メタデータ管理などの役割を担い、全体の制御と運用を行います。複数の機能が連携して処理を行い、負荷が他のワークロードに影響しない構造です。結果として、スケーラビリティ、可用性、セキュリティに優れたデータ基盤を実現しています。
クエリ処理(コンピュート)
クエリ処理(コンピュート)層では、仮想ウェアハウスと呼ばれる仮想マシンによってSQLクエリが実行されます。負荷に応じて動的にスケールイン・スケールアウトでき、必要なリソースを柔軟に確保できます。
データベースストレージ
データベースストレージ層では、クラウドストレージにデータを一元的に格納します。また、格納したデータは自動的に圧縮及び暗号化されるため、ユーザーが直接アクセスすることはなく、クエリ処理でのみアクセスが可能です。
Snowflakeの特徴
柔軟なスケーラビリティ
Snowflakeの大きな特長の一つが、柔軟なスケーラビリティです。ストレージとコンピュート(処理)を完全に分離した設計により、ユーザーは必要な時に必要な処理能力だけを動的に拡張できます。例えば、アクセスが集中する時間帯だけ仮想ウェアハウスを自動でスケールアップし、通常時にはリソースを縮小してコストを抑えることが可能です。一方で大規模データを格納したい場合は、データベースストレージのみを拡張できます。
利用量に応じたコスト適正化
Snowflakeは使った分だけ料金が発生する、従量課金モデルを採用しています。コンピュートとストレージが分離されているため、両方を常時フル稼働させる必要はありません。そのため、不要なリソースは利用しないことでコストの無駄を大幅に削減できます。例えば、データ分析の頻度が少ない場合はコンピュートリソースを停止し、ストレージのみの料金で済ませられます。これにより、企業は必要最小限の投資で最大限のパフォーマンスを引き出せます。
フルマネージドサービス
Snowflakeはフルマネージド型のクラウドサービスです。そのためインフラの構築・運用・メンテナンスがクラウド側で自動的に処理されます。ユーザーはサーバーの設定やパッチ適用、バックアップといった煩雑な運用作業を行う必要がありません。
また、可用性やセキュリティの面でも充実しており、自動復旧や災害対策も標準機能として備えています。また、UIも直感的で、SQLを中心とした操作が可能です。このように運用・保守の面でもユーザーにとって扱いやすいという優れた特長があります。
マルチクラウドに対応
Snowflakeは、主要なクラウドプロバイダーであるAWS(Amazon Web Service)、Microsoft Azure、Google Cloudに対応しています。これにより、ユーザーは自社のクラウド戦略やインフラに合わせてデータ連携が可能です。また、クラウド間でのベンダーロックインを回避できるという点も優れています。
Snowflakeの用途
データウェアハウス
Snowflakeは、主な用途として挙げられるのが、データウェアハウスです。従来のオンプレミス型と違い、容量制限の心配がなく大量データを高速かつ安定的に処理できる点や、分析用途に応じてリソースを柔軟に調整できる点も優れているからです。また画像などの非構造化データ以外にも半構造化データ(JSON、Parquetなど)も扱えるため、データウェアハウスの枠を超えた汎用性を持っています。
データ共有
Snowflakeでは、クラウド上でデータを一元管理しているため、データ共有が容易です。従来のデータ連携ではデータのコピーやファイル転送が必要でしたが、Snowflakeではクラウドプラットフォーム上で安全かつリアルタイムに共有が可能です。これにより、無駄なストレージ消費を抑えつつ、常に最新データを共有できます。例えば、サプライヤーと在庫情報を共有したり、パートナー企業と市場データをリアルタイムでデータをやりとりすることも可能です。
AIデータクラウド
Snowflakeは「AIデータクラウド」としても活用が進んでいます。構造化、半構造化、非構造化問わず大量のデータを効率的に管理・統合できるため、AIや機械学習モデルの開発に最適です。また、PythonやRといったデータサイエンスの言語や、SageMakerやDataRobotなどのサービスとの連携も容易であり、AI開発のワークフローを効率化できます。
マーケットプレイス
Snowflakeには「データマーケットプレイス(Snowflake Marketplace)」という機能があります。これを利用することで、企業が保有するデータセットを販売・共有することが可能です。例えば、天候のデータや人口統計などの分野で有益なデータを共有し即座に分析に取り入れることで新たな洞察を得られます。データプロバイダーにとっても、自社のデータ資産を収益化する手段として活用可能です。
Snowflakeと競合サービスとの違い
Snowflakeのようなクラウドベースのデータウェアハウスのサービスは他にもあります。ここでは競合サービスとの違いをまとめてみました。
|
サービス |
Snowflake |
Amazon Redshift |
Google BigQuery |
Azure Synapse |
|
対応クラウド |
マルチクラウド |
AWSのみ |
Google Cloudのみ |
Microsoft Azureのみ |
|
構成 |
コンピュートとストレージが分離 |
シェアードナッシング+超並列処理 |
サーバーレスアーキテクチャ |
サーバーレスアーキテクチャ |
|
ユーザーによる管理 |
フルマネージド |
一部管理が必要 |
フルマネージド |
一部管理が必要 |
|
課金体系 |
コンピュート、ストレージ従量課金 |
コンピュートベースの固定料金が基本 |
クエリベース(読み込みデータ量) |
クエリベースまたはオンデマンド |
まとめ
本記事では、Snowflakeについて解説しました。Snowflakeは、柔軟なスケーラビリティやコスト最適化、マルチクラウド対応という特長をもち、多くの企業で高く評価されています。またさまざまな用途で利用でき、データウェアハウスとしての利用だけでなく、データ共有やAI開発、マーケットプレイスなど、あらゆるデータ活用のハブとして機能します。
今後もデータ分析基盤やAIデータクラウドとして、Snowflakeはビジネスにおける迅速な意思決定を目指す企業にとって欠かせない選択肢と言えるでしょう。
- カテゴリ:
- キーワード:


![いまさら聞けない Oracleの基本[初級編]](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/2975556/interactive-176098890646.png)
![いまさら聞けない Oracleの基本[初級編]](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/2975556/interactive-176098890651.png)


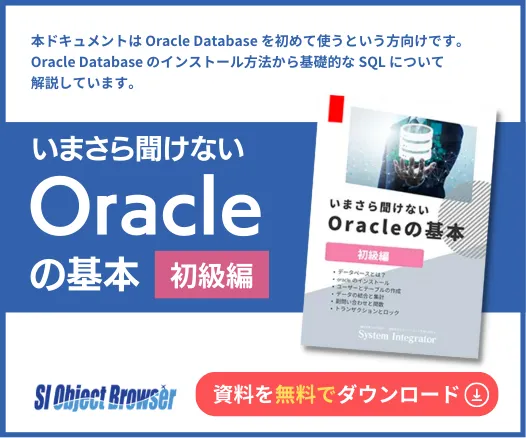





![いまさら聞けない Oracleの基本 [初級編]](https://products.sint.co.jp/hubfs/images/siob/thumb/ora_b.png)
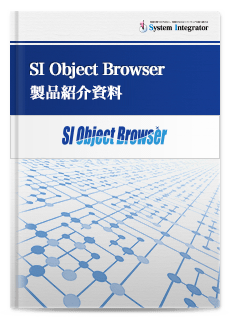
![いまさら聞けない Oracleの基本 [中級編]](https://products.sint.co.jp/hubfs/images/siob/thumb/ora2.webp)
![いまさら聞けない Oracleの基本[初級編]](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/2975556/interactive-176098890654.png)