システムの利用形態として従来は、自社内にサーバーやネットワークなどITインフラを敷設してシステムを構築・運用する「オンプレミス」が主流でした。その後インターネットを介してITインフラを利用する「クラウド」が普及してきました。
オンプレミス、クラウドどちらもメリット・デメリットがあります。どちらか一方でないでないといけないことはなく、両方を組み合わせた「ハイブリッドクラウド」という形態も存在します。
本記事では、ハイブリッドクラウドについて、活用事例も踏まえて詳しく解説します。
ハイブリッドクラウドの基本知識
ハイブリッドクラウドとは
ハイブリッドクラウドは、オンプレミスとクラウドを組み合わせたシステムの形態です。クラウドには、自社でクラウドサービスを占有できる「プライベートクラウド」と、利用ユーザーでリソースを共有する「パブリッククラウド」があります。
また、プライベートクラウドはさらにITインフラを自社内に配置するオンプレミス型と、クラウドサービスを利用するホスティング型に別れます。
それぞれのシステム形態を以下の表にまとめました。
|
システム携帯 |
ITインフラ |
リソースの利用 |
メリット |
デメリット |
|
オンプレミス |
自社内で構築 |
占有 |
・カスタマイズ性が高い |
・初期コストが高い |
|
プライベート |
自社内で構築 |
占有 |
・カスタマイズ性が高い |
・初期コストが高い |
|
プライベート |
クラウド |
占有 |
・初期コスト、運用コストを抑えられる |
・カスタマイズに制限がある |
|
パブリック |
クラウド |
共有 |
・初期コスト、運用コストを抑えられる |
・カスタマイズに制限がある |
上記表のとおり、オンプレミスやプライベートクラウドは自社にデータを保持できるためセキュリティが高く、パブリッククラウドはスケーリングがしやすいというメリットがあります。ハイブリッドクラウドはこれらのメリットを踏まえ、オンプレミスやプライベートクラウド、パブリッククラウドを組み合わせてシステムを構築する形態です。
ハイブリッドクラウドに適したシステムとは
ハイブリッドクラウドは、全てのシステムをクラウドに移行するのが難しい、または特定のシステムに高いセキュリティやコンプライアンス要件が求められる場合に特に適しています。
例えば、機密性の高いデータを扱う基幹システムは、セキュリティが強固なオンプレミスまたはプライベートクラウドで管理し、一方で、Webアプリケーションや開発環境、ビッグデータ分析など、柔軟性やスケーラビリティが求められるシステムは、パブリッククラウドで運用します。
ハイブリッドクラウドにより、システムの特性や要件に応じて最適な環境を選択することで、セキュリティやコスト、パフォーマンスなどのバランスがとれたITインフラを実現できます。
ハイブリッドクラウドのメリット
要件に応じて柔軟な構成が可能
ハイブリッドクラウドでは、オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウドを組み合わせ、多様なニーズに柔軟に対応できます。機密性の高いデータはセキュリティが高いオンプレミスに、処理能力が求められるWebシステムはスケーラビリティの高いパブリッククラウドに配置するなど、最適なリソース配分を実現できます。
コストパフォーマンスがよい
ハイブリッドクラウドは、コストパフォーマンスに優れています。オンプレミスやプライベートクラウドは初期投資が必要な分、長期的に見るとコストを抑えられます。また、パブリッククラウドは一般的に従量課金制であり、利用した分だけ費用が発生するため必要以上のランニングコストのムダを削減できます。
この特性を活かし、利用負荷が高いものをオンプレミスに、リソースの消費変動が激しいものはパブリッククラウドを利用することでコストを削減できます。
負荷の軽減、リスク分散につながる
ハイブリッドクラウドは、システムを複数の環境に分散して配置するため、システム全体の負荷の軽減およびリスク分散に繋がります。例えば、パブリッククラウド側で障害が発生しても、オンプレミス側でシステムを継続できます。
ハイブリッドクラウドのデメリット
構成が複雑になり、管理工数が増加
ハイブリッドクラウドは、オンプレミス環境とパブリッククラウドなどを組み合わせるため、システム構成が複雑になりがちです。異なる環境間の連携やデータ移行、監視、セキュリティ対策などを適切に行うには、専門的な知識と経験が求められます。
コスト計算が難しい
ハイブリッドクラウドでは、コスト計算が複雑になる傾向があります。なぜなら、オンプレミスとクラウドでコストの内容が異なるためです。オンプレミス環境の初期投資や運用コスト、パブリッククラウドの従量課金など、異なるコスト構造を把握し、最適化する必要があります。
専門知識を持った人材の確保が必要
ハイブリッドクラウドの導入・運用には、高度な専門知識を持った人材が不可欠です。複数のクラウド環境やオンプレミス環境以外にもネットワーク、セキュリティなど、幅広い知識と経験を持つ人材が必要です。このような人材の育成や確保は容易ではなく、人材不足がハイブリッドクラウド導入の障壁となる可能性があります。
ハイブリッドクラウドの活用事例
アプリケーションとデータを分けた構成
ハイブリッドクラウドの活用事例として、アプリケーションとデータを分離した構成が挙げられます。例えば、セキュリティが求められるアプリケーションはプライベートクラウドに、Webアプリケーションなどの公開情報はスケーラビリティの高いパブリッククラウドに配置します。これにより、セキュリティとパフォーマンスの両立を実現できます。
データの機密性を考慮した構成
ハイブリッドクラウドは、データの機密性に応じた構成をとることができます。例えば、個人情報や財務情報などの機密データは、自社のセキュリティポリシーに合わせたプライベートクラウドに保管します。
一方、公開情報や一時的なデータは、コスト効率の良いパブリッククラウドを利用します。
BCP対策
ハイブリッドクラウドは、BCP(事業継続計画)対策としても有効です。例えば、オンプレミス環境で普段運用している基幹システムを、災害時に備えてパブリッククラウドにバックアップしておきます。これにより、万が一オンプレミス環境が被災した場合でも、迅速にパブリッククラウドに切り替えて事業を継続できます。
まとめ
本記事では、ハイブリッドクラウドについて解説しました。ハイブリッドクラウドは、オンプレミスおよびプライベートクラウドと、パブリッククラウドのそれぞれの利点が得られる構成です。
トランザクション量の変化が激しい場合や、機密性の高いデータを扱う場合など厳しい要件に対して柔軟に対応できます。ただし、構成が複雑となり管理が難しいため、専門知識をもった人材が求められます。要件や状況に応じて、ハイブリッドクラウドの構成も検討するとよいでしょう。
- カテゴリ:
- キーワード:


![いまさら聞けない Oracleの基本[初級編]](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/2975556/interactive-176098890646.png)
![いまさら聞けない Oracleの基本[初級編]](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/2975556/interactive-176098890651.png)


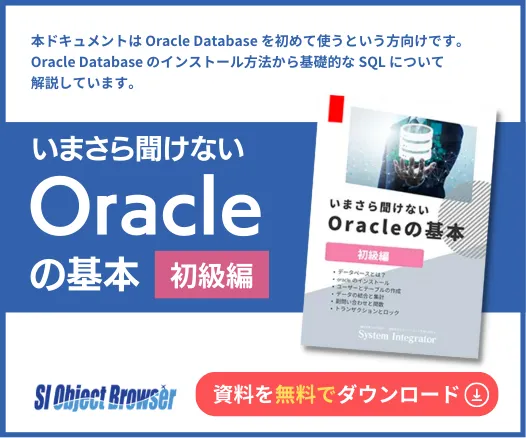





![いまさら聞けない Oracleの基本 [初級編]](https://products.sint.co.jp/hubfs/images/siob/thumb/ora_b.png)
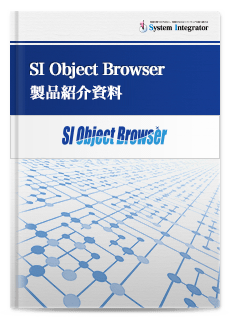
![いまさら聞けない Oracleの基本 [中級編]](https://products.sint.co.jp/hubfs/images/siob/thumb/ora2.webp)
![いまさら聞けない Oracleの基本[初級編]](https://hubspot-no-cache-na2-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/2975556/interactive-176098890654.png)