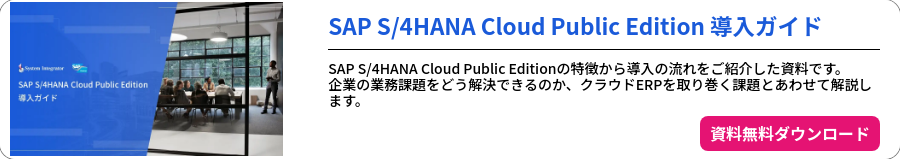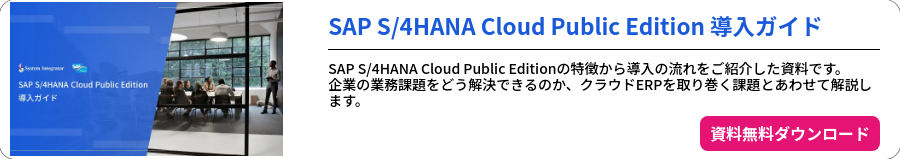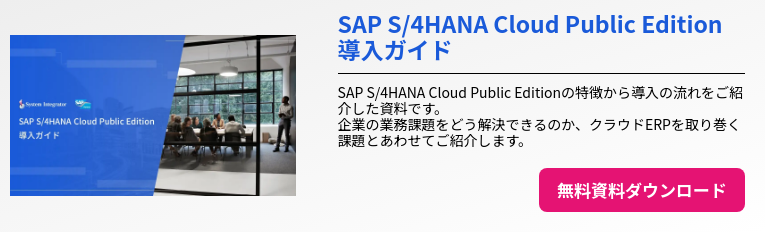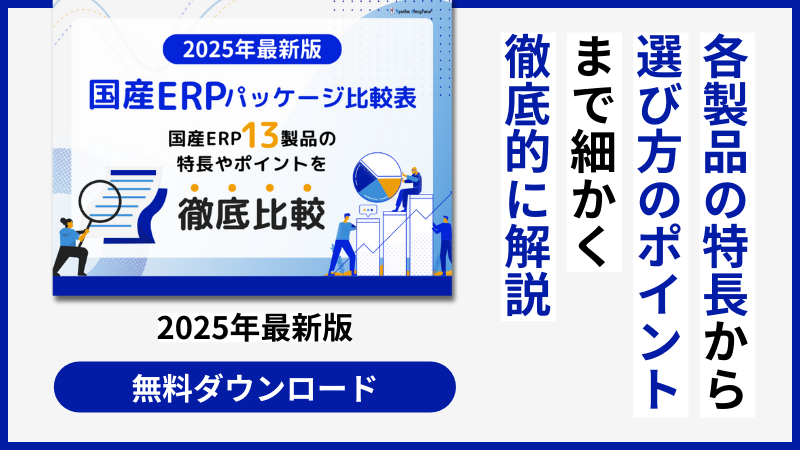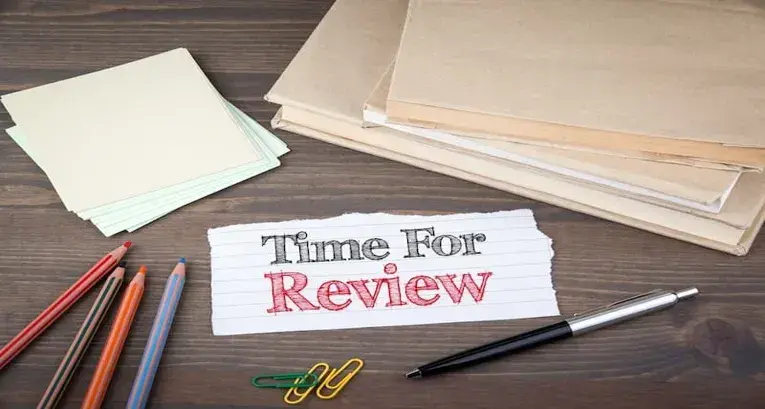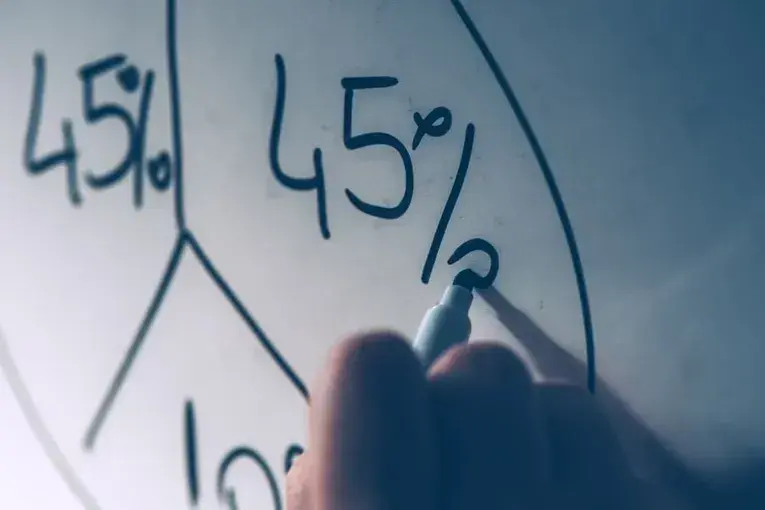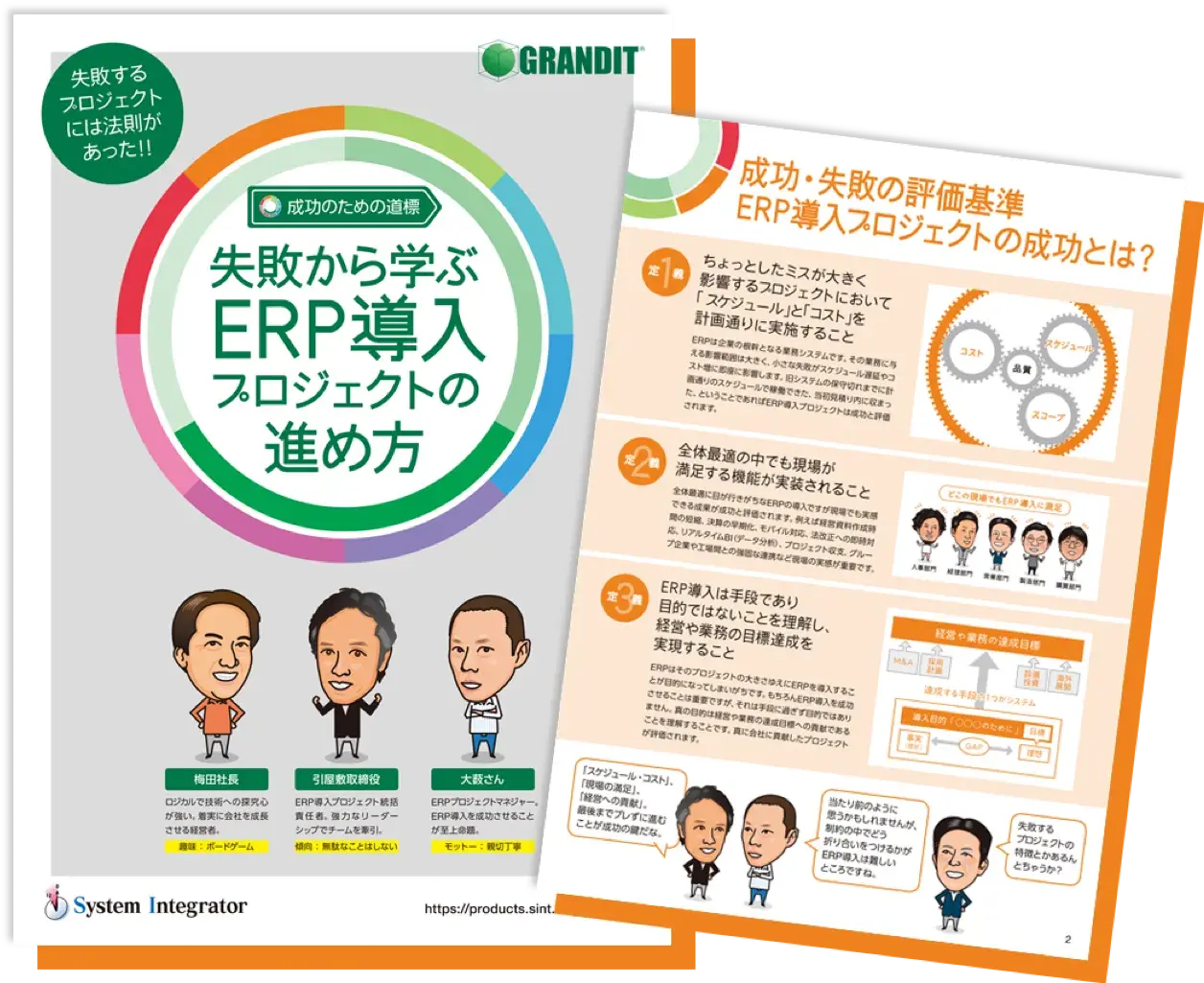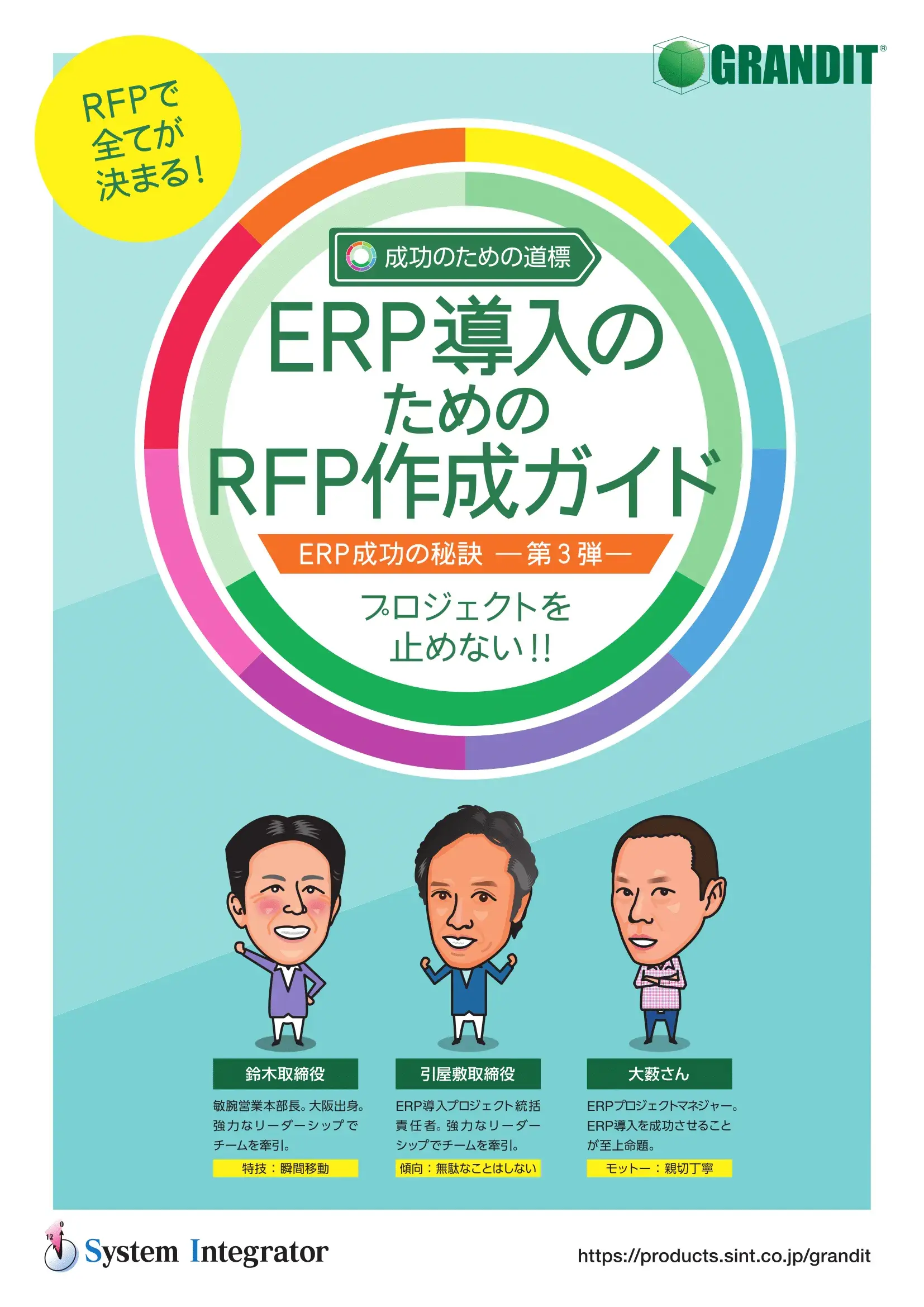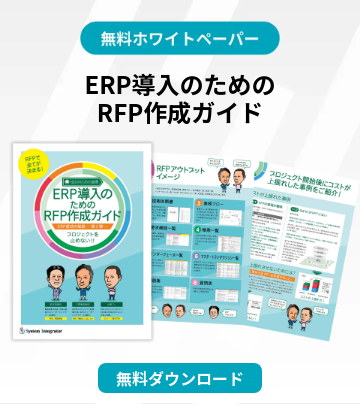多くの企業で導入されている「SAP ERP」は、スピード経営の実現や業務効率化、さらにはテレワーク推進にも役立つ便利なツールです。しかし、このシステムのサポートがまもなく終了することをご存じでしょうか。このタイミングを機に、システムの見直しを検討している企業も少なくありません。
本記事では、SAP ERPの基本情報や一般的なERPシステムとの違い、導入のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
SAP ERPとは

SAP ERPは、ドイツ・ヴァルドルフに本社を構える「SAP社」が提供する統合基幹業務システム(ERP)です。SAP社は1973年に世界初のERPシステム「SAP R/1」をリリースして以来、ERP市場のリーディングカンパニーとして、世界中の企業にソリューションを提供してきました。
豊富な経験と最新技術を活かして、時代のニーズに即したERP製品を展開しており、現在ではグローバル企業はもちろん、中堅企業や国内企業にも広く導入されています。
さらに、SAP社が提供するERP製品は単なるERPにとどまらず、経営分析やレポーティングを可能にする「SAP BW」、需要予測や生産計画の最適化を支援する「SAP APO」などの機能と連携することで、より高度な業務改革が実現できます。
SAP社が提供するERPの種類
SAP社がこれまでに提供してきたERPジは、以下のように世代ごとに分類されます。
- 世界初のERP:SAP R/1(1973年)
- 第1世代:SAP R/2(1979年)
- 第2世代:SAP R/3(1992年) → 後に「ECC」と呼ばれる
- 第3世代:SAP S/4HANA(2015年〜 現在の主力製品)
一般に「SAP ERP」と呼ばれるのは、主にSAP R/3を指します。現在では、これらの後継となるSAP S/4HANAへの移行が進んでおり、高速なデータ処理、クラウド対応、ユーザーインターフェース(UI)の改善などが主な特長です。
SAPについては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
SAPとは?ドイツ発ERPの特徴や導入のポイントを解説
そもそもERPとは
近年では、「ERP=統合基幹業務システム」という意味で使われることが多く、調達・購買管理や販売・出荷管理、生産管理、会計・財務、在庫管理など、企業のさまざまな業務を一つのシステムで統合的に管理することができます。
このような情報の一元化により、業務効率の向上、部門間の連携強化、そしてリアルタイムな経営判断が可能になります。
ERPについては、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
ERPとは?統合基幹システムの種類やメリットなどを解説
SAP ERPの機能とは?

SAP ERPは、企業活動に必要なさまざまな業務機能を「モジュール」として体系化し、それらを一元管理できる統合システムです。各モジュールはリアルタイムで連携しており、部門間での情報共有や業務効率化を強力に支援します。ここでは、代表的なモジュールをご紹介します。
会計モジュール
-
FI:財務会計(Financial Accounting)
仕訳、決算、税務、財務報告などを一元管理。IFRSなど国際会計基準にも対応。
-
CO:管理会計(Controlling)
原価計算、部門別損益、予実管理など、経営分析に必要な情報を可視化します。
ロジスティクスモジュール
-
SD:販売管理(Sales and Distribution)
受注・出荷・請求などを統合的に管理し、顧客対応の迅速化を図ります。
-
MM:在庫購買管理(Material Management)
調達先管理、在庫最適化、購買予測など、サプライチェーン全体の効率化を実現します。
人事モジュール
-
HR:人事管理(Human Resources)
従業員情報の一元化から、勤怠・評価・人材育成までフルカバー。
生産管理モジュール
-
PP:生産計画/管理(Production Planning and Control)
需要予測に基づいた製造計画、工程管理、生産コストの最適化に寄与します。
倉庫管理モジュール
-
WM:倉庫管理(Warehouse Management)
在庫ロケーション、入出庫、棚卸の自動化など、精度の高い在庫管理を実現します。
そのほかのモジュール
- QM:品質管理(Quality Management)
- PS:プロジェクト管理(Project System)
- PM:プラント保全(Plant Maintenance)
- CA:クロスアプリケーション(Cross Application)
このように、原価管理に役立つ会計モジュールから、人事・生産管理・在庫管理・プロジェクト管理まで、SAPひとつでプロジェクトから経営まで幅広くカバーできます。
いずれのモジュールもカスタマイズ性が高く、さまざまな企業の業務環境にマッチするようにできています。
SAP ERPと他のERP製品との違いは?
SAP ERPは多機能・高拡張性で世界的に導入されている一方、他のERP製品には導入しやすさや業種特化といった強みもあります。
ここでは、代表的な比較項目をもとにSAP ERPの特長を整理します。
| 比較項目 | SAP ERP | 他のERP |
|---|---|---|
| 業務領域のカバー範囲 | 販売・会計・人事・生産・在庫管理など、基幹業務はもちろん、CRMやSFA、SCMなどの機能もあり、SAP ERPのみで企業の業務のほとんどをカバーできる | 会計や販売など、基幹業務は包括されているが、業種や業務特化の機能はカバーされていないことがある |
| 拡張性・柔軟性 | 高度なカスタマイズが可能で、業種や業務ごとに柔軟に対応 | 製品によってはカスタマイズに制限がある |
| グローバル対応 | 多言語・多通貨・各国会計基準に対応。海外拠点も一元管理可能 | 国内中心の製品は国際対応に制限があることも |
| 導入実績 | 世界中の大企業で導入されており、ERP市場で圧倒的なシェア | 特定の業界や地域に限定された実績が多い |
SAP ERPは、グローバルな事業展開や複雑な業務管理を求める企業にとって、最適な選択肢となります。一方で、中小企業や業務範囲の限定された企業には、他のERP製品が適している場合もあります。
SAP ERPのメリット・デメリット

SAP ERPは、世界中の大企業で長年にわたり採用されてきた実績を持つ、高機能かつ柔軟性・拡張性に優れたERPシステムです。多様な業務領域に対応可能な一方で、導入や運用に際してはいくつかの課題も存在します。本章では、SAP ERPを導入する際に知っておくべきメリットとデメリットについて、詳しく解説します。
SAP ERPのメリット
-
業務全体をカバーする統合性の高いシステム構成
SAP ERPは、「受注・販売管理」「在庫管理」「生産管理」「財務管理」などの基幹業務から、「人事給与」「経費精算」「固定資産管理」「プロジェクト管理」「管理会計」「顧客管理」「予算管理」などの業務特化領域まで、幅広い業務プロセスを網羅しています。
このように、複数の業務を一つのシステム上で一元的に管理できるため、部門間で分断されがちなデータの連携が強化され、全社的な業務の可視化と効率化が実現します。
また、SAPは業務全体の整合性を重視した設計思想を持っており、特定業務のカスタマイズや変更が発生しても、システム全体の統一性が維持されやすいという利点があります。
-
グローバル対応と法制度順応
SAP社の強みは、グローバル企業への対応実績の豊富さにあります。多くの国と地域での導入経験があるため、他のERP製品と比較しても、グローバル対応機能の成熟度は非常に高く、実際の業務運用に即した設計がなされています。
特に、各国の法制度の変更にも柔軟かつ迅速に対応できる点は、海外拠点を持つ企業にとって大きな安心材料となります。法令対応のスピードや正確性が高いという点は、SAPが長年にわたり信頼を積み上げてきた証でもあります。
-
データ活用ができる
インメモリデータベースである「SAP HANA」を採用していることで、大量の業務データをリアルタイムに処理・分析することが可能です。これにより、従来は時間のかかっていた集計や分析作業も迅速化され、よりタイムリーな意思決定を支援します。
また、SAPが提供するBI(ビジネスインテリジェンス)ツールと連携することで、経営層向けのKPIの可視化や、将来を見据えたシミュレーションも簡単に行えるようになっています。データドリブンな経営を実現するための基盤として、大きな価値を持つ機能です。
SAP ERPのデメリット
-
初期導入コストと長期的な維持費用の高さ
SAP ERPは多機能・高性能なシステムであるため、ライセンス料やサーバー費用、構築費用などの初期導入コストが高くなりがちです。さらに、業務要件に応じて追加機能やカスタマイズを行う場合は、それに伴う開発費が発生するケースもあり、全体の費用がさらに膨らむ傾向にあります。ERP市場全体で見ても、SAPは比較的高価格帯に位置する製品であるといえるでしょう。
また、SAPはユーザー数に応じたライセンス体系を採用しており、ユーザーが多いほどコストは増加します。費用を抑えるために無理にユーザー数を減らすと、業務の滞りや操作権限の不具合などが発生しやすくなり、結果的に導入そのものが失敗する可能性もあるため注意が必要です。
-
専門知識と人材の確保が不可欠
SAP ERPは非常に多機能でカバー範囲も広いため、システムを適切に活用するには、製品に対する専門的な知識が欠かせません。実際の導入プロジェクトでも、SAPに精通したコンサルタントの支援を受けることが一般的です。また、導入には複数部門が関与する必要があり、企業全体を巻き込んだ取り組みとなることから、一定の体制整備が求められます。
プロジェクトの規模が大きくなるほど、スケジュールも長期化しやすく、導入後に運用が定着しないといったリスクも高まります。そのため、導入前の準備段階から明確な目的設定と社内調整が不可欠となります。
クラウド化による導入ハードルの低下
近年では導入のハードルが下がってきているのも事実です。SAP S/4HANA® Cloud Public EditionといったクラウドERPの登場により、オンプレミス型よりも短期間・低コストでの導入が可能になっています。また、標準機能に業務を合わせる「Fit to Standardアプローチ」が普及したことで、カスタマイズの必要性が減り、導入の複雑さも軽減されています。
SAP S/4HANA® Cloud Public Editionについてはこちらをご覧ください。
SAP S/4HANA® Cloud Public Editionご紹介ページ
SAP ERP 2027年問題:サポート終了と今後の対応

SAP ERP(SAP R/3/ECC)を利用している企業にとって、避けて通れないのが「2027年にメインストリームサポートが終了する問題」です。
長年にわたって多くの企業の基幹業務を支えてきたSAP ERPですが、現在は後継システム「SAP S/4HANA」への移行が推奨されており、各社は今後の対応方針を早めに決める必要があります。
なぜサポートが終了するのか?その背景と影響
当初、SAP ERP のメインストリームサポートは2025年に終了する予定でしたが、2020年にSAP社が2027年まで延長すると発表しました。さらに、EhP(エンハンスメントパッケージ)6~8を使っている企業に限り、追加保守契約を結ぶことで2030年までサポートを受けられるようになっています。
ただし、サポートが終了すると、以下のようなリスクが生じます:
- 税制や法制度の改正に対応できない
- セキュリティパッチやバグ修正の提供がストップ
- 機能の拡張や最適化が止まり、業務効率が低下
- 内部統制や監査への対応が難しくなる
これらのリスクは、事業継続に直接影響する可能性があるため、早めの移行戦略の検討が重要です。
S/4HANAへの移行と課題
SAPの次世代ERP「SAP S/4HANA」は、インメモリデータベース「HANA」を基盤にしており、高速処理やリアルタイム分析が可能。さらに、AIや機械学習の活用、クラウド対応、モダンなUI(SAP Fiori)など、従来のERPに比べて多くの機能が強化されています。
ただし、移行は単なるシステムの入れ替えではありません。以下のような課題もあります。
- プロジェクトが長期化する可能性
- 現行システムとのカスタマイズの整合性確認
- 社内リソースの確保や外部パートナーの選定
- ライセンスや構築、トレーニングにかかるコスト
特に大規模なシステム移行では、業務全体の見直しとリスク管理が不可欠です。
企業が選べる3つの対応策
SAP ERPを利用中の企業には、次のような選択肢があります。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| ① S/4HANAへの移行 | SAPが推奨する方法。最新機能が使え、長期サポートも受けられるが、準備と投資が必要。 |
| ② 現行ERPの延命(保守延長) | EhP6~8を利用していれば、追加保守契約で2030年まで延長可能。ただし、将来的な移行は避けられない。 |
| ③ 他社製ERPへの切り替え | コストや業務要件に合ったシステム選定が可能。業務再設計が伴うため、導入の難易度は高め。 |
いずれを選ぶにしても、現状の把握と将来を見据えた計画づくりがカギになります。
詳しい情報は、こちらの記事をご覧ください。
SAP ERPの2027年問題について
SAPだけじゃない!主要ERPパッケージの比較と導入検討の視点

これまで、SAP ERPの概要やその強み・課題についてご紹介してきました。
しかし近年では、2027年のサポート終了(いわゆる「2027年問題」)や移行に伴う負担の大きさを受け、他社製ERPの導入を検討する企業が増えてきています。
本章では、SAP ERPとよく比較される代表的なERP製品を3つピックアップし、それぞれの特徴や導入の適性を解説します。ERP選定の参考としてお役立てください。
GRANDIT:日本企業に最適化された純国産ERP
「GRANDIT」は、株式会社システムインテグレータが提供する純国産ERPです。クラウド・オンプレミスのどちらにも対応し、製造業・情報サービス業・商社・小売業など、1,400社以上の導入実績があります。
開発は、11社のプライムパートナーによるコンソーシアム方式で行われており、各社のノウハウを結集した“現場目線”の機能が特徴です。
共通機能として、電子承認ワークフロー、メール・Web通知、データ分析、EC連携、海外取引対応などを標準搭載。コストや導入ハードルを抑えたい中堅企業にとって、現実的で有力な選択肢となります。
Oracle:グローバル対応に優れたクラウドERP
オラクルが提供するERPには、「Oracle NetSuite」と「Oracle Cloud ERP」の2種類があり、どちらもクラウドベースで提供されています。
- Oracle NetSuite:クラウドネイティブなERPで、ERP・CRM・EC機能を統合。多言語・多通貨に対応しており、グローバル展開を視野に入れた企業に最適です。
- Oracle Cloud ERP:高い柔軟性とパフォーマンスを備えたクラウドERP。オンプレミス並みの性能に加え、強固なセキュリティも特徴。業務が複雑な大企業や多拠点展開企業に向いています。
OBIC7:安定志向の企業に選ばれる国内トップシェアERP
「OBIC7」はオービックが提供するERP製品で、累計2万7,000社以上の導入実績を誇ります。2022年度には、ベンダー別ERP売上金額で国内第1位を記録しました。
自社開発・直接販売体制を一貫して継続しており、サポートの手厚さにも定評があります。
会計・人事・給与・販売・生産・クラウドなど、10種類以上の業務機能を柔軟に組み合わせて導入可能。シンプルながらカスタマイズ性が高く、導入しやすい点が支持されています。
まとめ:ERP選定は経営戦略そのもの
SAP ERPは、世界中の大手企業に採用されてきた信頼性の高いシステムであり、成長やグローバル展開、業務効率化を支える重要な基盤です。
しかしながら、2027年のサポート終了や、S/4HANAへの移行にかかるコスト・手間といった現実的な課題が存在します。多くの企業が今、次の一手を模索している状況です。
本記事では以下の観点から整理を行いました。
- SAP ERPの機能とメリット/デメリット
- 2027年問題に伴う移行の必要性と課題
- 主要ERP(GRANDIT/Oracle ERP/OBIC7)の比較と導入適性
ERPの選定は、単なるシステム更新ではなく、中長期の経営戦略や業務プロセスを見直す絶好の機会でもあります。現状の課題や将来のビジョンを踏まえ、最適なパートナーとソリューションを選ぶことが、成功への第一歩です。
ERPなら株式会社システムインテグレータ にご相談ください。
また、弊社では、ERPパッケージ比較資料やERPを選定する際のポイントをまとめた資料などを多数ご用意しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。