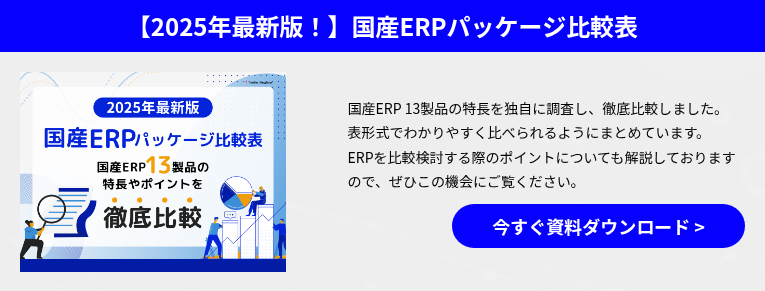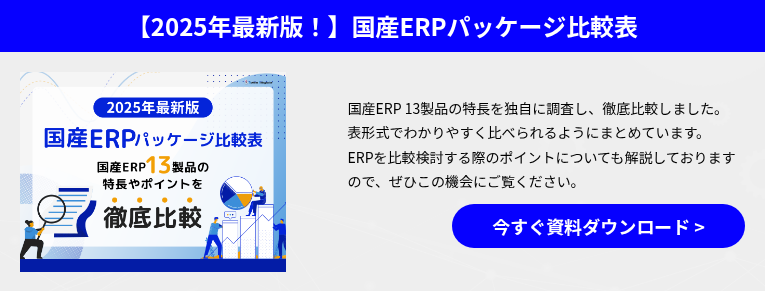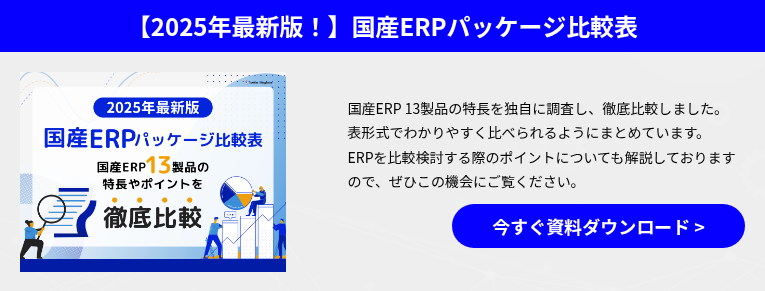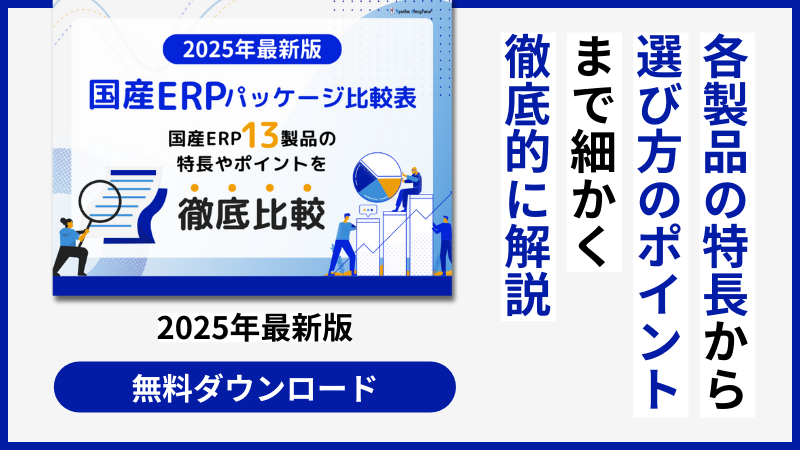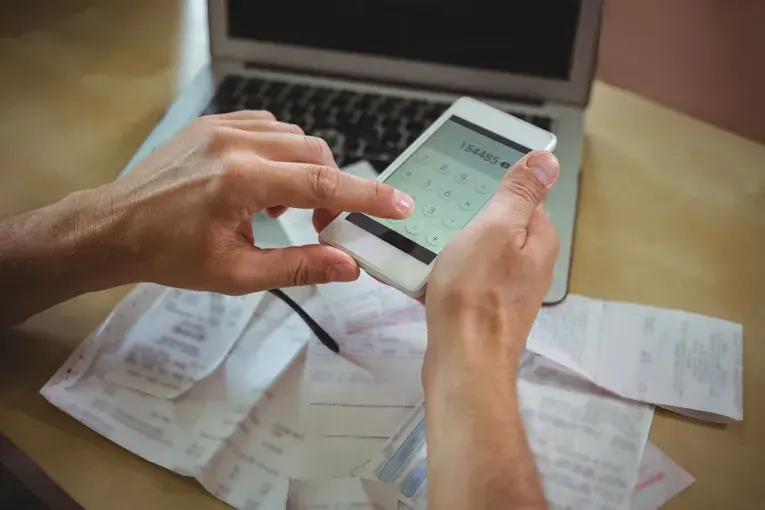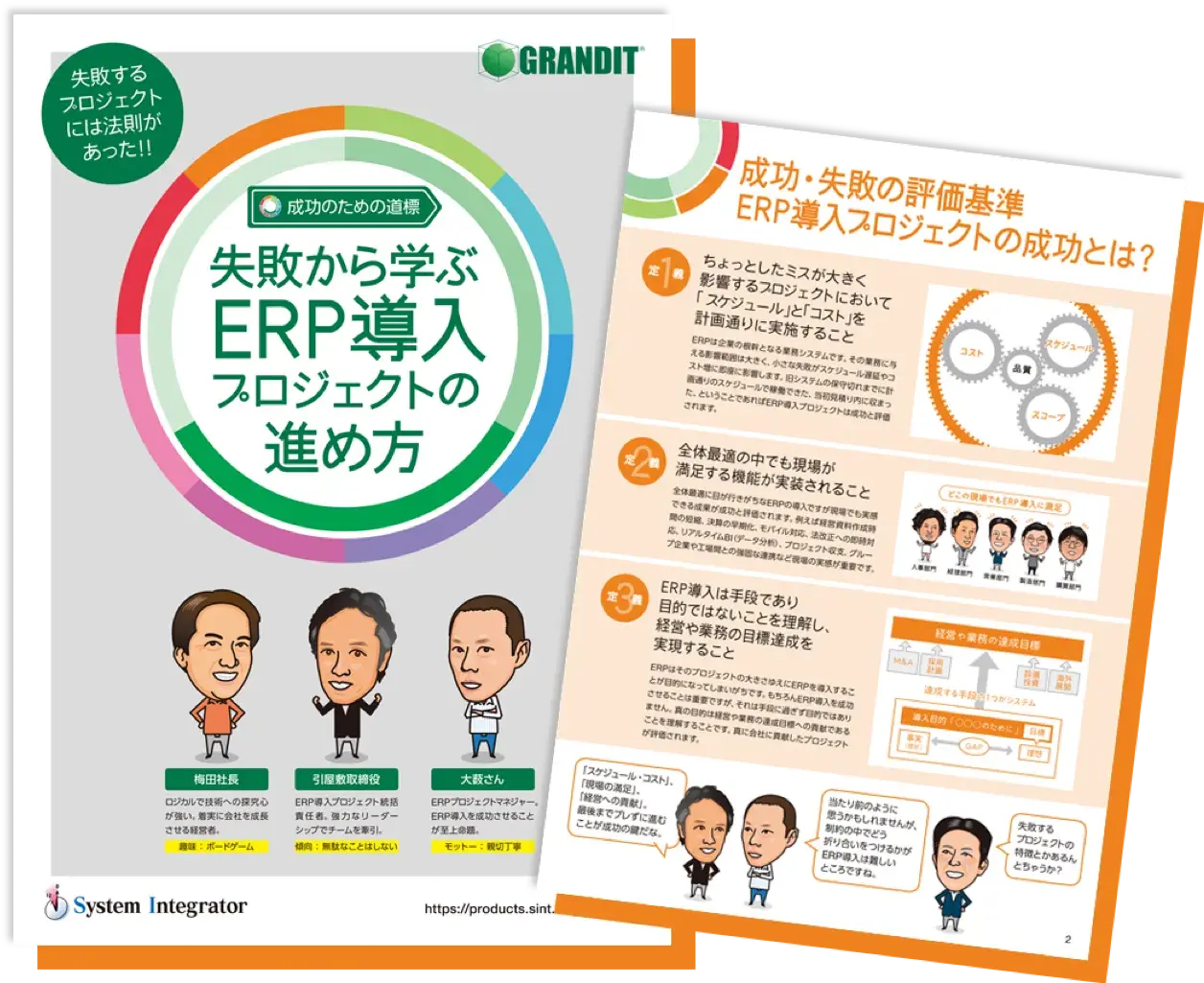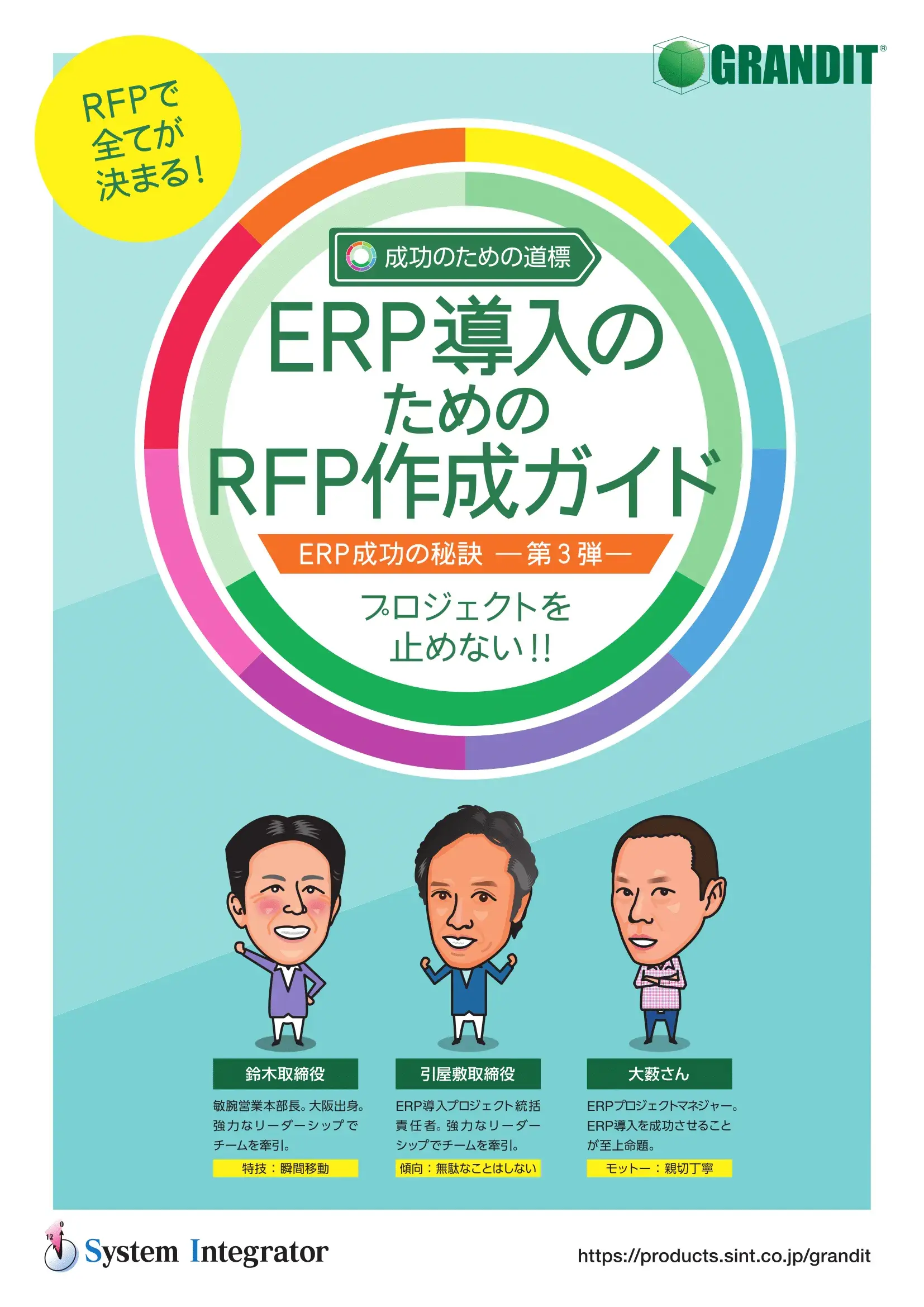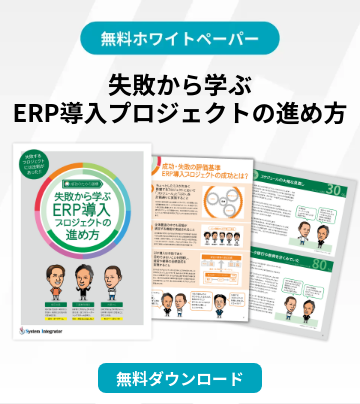企業活動の基盤として導入されることが多いERPシステム。
会計や販売管理、在庫管理など基幹業務にまつわるデータを一元管理する役割を果たします。しかし、社内にはほかにも多数の業務システムが存在し、これらと連携して更なる業務効率化を図りたい方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、まずERPの概要や種類、外部システムの連携方法などを解説します。これからERPと外部システムを連携させる予定のある方はぜひご覧ください。
ERPとは

ERP(Enterprise Resource Planning)は、会計や販売、在庫、人事など企業の主要業務情報を一つのシステムで一元管理し、重複入力やデータ整合性の問題を解消するのが狙いです。
国内外の大企業だけでなく、中堅・中小企業にも導入が広がっており、クラウド技術の進歩によって初期コストが抑えられるようになったことも普及を後押ししています。
従来、部門ごとに別々のソフトを使っていた場合、全社的な視点でのリアルタイムデータ把握が困難になり、経営判断の遅れやミスの原因となりがちでした。
ERPを導入すれば、販売管理で行った受注処理が会計にも即時反映され、在庫管理システムとも連動できるため、同じ情報を二重・三重に入力する手間が削減されます。
ERPによって、経営者や管理部門も正確な数値をリアルタイムに参照しやすくなるでしょう。
ERPの種類

ERPと一口にいっても、導入形態や機能構成によって複数の種類があります。
ERPは以下のように分類されます。
- クラウド型のERP
- オンプレミス型のERP
- 統合型のERP
- コンポーネント型のERP
順に解説します。
クラウド型のERP
クラウドベンダーが用意するインフラを活用し、インターネット経由で使うERPです。サーバーの準備や保守運用をベンダー側が担当するため、初期コストを抑えやすく、導入スピードが速いのがメリットです。外部システムとの連携においても、APIを使った接続が標準的に用意されていることが多く、開発工数を縮小できるケースがあります。
一方で、カスタマイズ範囲が制限されやすく、自社固有の業務要件を盛り込みにくい面があります。また、インターネット越しにやり取りする以上、セキュリティ要件や通信速度を考慮して選択することが重要になります。
オンプレミス型のERP
自社サーバーやデータセンターにERPをインストールして運用する形式です。セキュリティやカスタマイズ性を自社主導でコントロールできるため、大企業や機密度の高いデータを扱う業種に根強い人気があります。
しかし、サーバー構築やソフトウェアライセンス、保守要員の確保など、初期コストと運用負荷が大きい点がデメリットです。外部システムとの連携では、社内ネットワークにセキュアなAPIやVPN接続を設ける必要があり、構築や設定に時間がかかる場合があります。
統合型のERP
会計、在庫、販売、購買、人事給与など、複数の機能をあらかじめ統合して提供するERPパッケージです。スイート製品とも呼ばれ、必要な機能がモジュールごとに完備されているため、スムーズに全社展開できる利点があります。主に大手ベンダーが提供し、世界中の企業に導入実績があるものも多いです。
統合型であれば、機能間の連携は初めから最適化されているため、同一ベンダー製品内のデータ交換は比較的容易です。
また、外部システムとの連携にはベンダー独自のAPIや導入コンサルティングが必要になることもありますが、最近のパッケージバージョンでは標準APIや連携ツールが充実しており、比較的容易なケースも増えています。
コンポーネント型のERP
従来の統合型と異なり、各モジュールを個別に選んで組み合わせられるERPがコンポーネント型です。たとえば、会計モジュールだけ先行導入してから在庫・購買モジュールを追加するなど、段階的に拡張しやすいのが特徴です。
自社の業務プロセスにあわせて柔軟に構成を変えられる一方、ベンダーやバージョンが異なるモジュール同士を連携させる際、インタフェースの調整が必要になります。
外部システムとの接続も含め、連携仕様をしっかりと設計しないと、データ整合性の問題が起きる可能性があります。
ERPと外部システムの連携方法

ERPと外部システムを連携させるには、以下のような方法があります。
- データベース連携
- ファイル連携
- API連携
- Webサービス連携
順に解説します。
データベース連携
ERPのデータベースと外部システムのデータベースを直接やり取りして、必要な情報を更新・参照する方法です。SQLクエリを実行してテーブルを読み書きする形になり、大量データのやり取りが高速かつ効率的に行える場合があります。
ただし、ERPのデータベース構造がバージョンアップで変更されたり、ベンダーのサポートポリシーによって直接アクセスを推奨していなかったりすることもあるので、運用上のリスクやサポート対応について注意が必要です。
ファイル連携
CSVやXMLなどのファイル形式でデータを出力し、外部システムがそのファイルをインポートするという従来から使われている方法です。バッチ処理の形で定期的にファイルを受け渡すケースも多く、シンプルに実装できる点がメリットです。
ただし、リアルタイム性に欠けるため、即時更新が求められる業務にはあまり向きません。ファイル転送時のセキュリティ(暗号化や認証)をどう確保するかも大きな課題です。利用時には、ファイルフォーマットや命名規則を厳密に取り決める必要があります。
API連携
API(Application Programming Interface)を経由してERPと外部システムが相互にデータをやり取りする方法です。近年はRESTやGraphQLなどのAPIを使った連携が一般的となり、クラウド型のERPでは標準でAPIを公開しているベンダーも多くあります。
リアルタイム連携や小分けのデータ取得がしやすく、アプリケーションレベルで認証や暗号化を設定できるため、柔軟かつ安全な接続が実現しやすいです。一方、API仕様の変更やバージョン管理など、メンテナンス面の負担が発生する可能性があります。
Webサービス連携
SOAPやWSDLなどのWebサービスプロトコルを利用した連携形態です。API連携と似た概念ですが、SOAPの場合はXMLベースのメッセージ交換を行い、細かなエラーコードやセキュリティ要件をプロトコルレベルで扱う仕様が用意されています。
レガシーなシステムがSOAP Webサービスを導入しているケースもあるため、エンタープライズ環境や大手企業の社内サービス連携で依然使われることがあります。REST APIほど軽量・シンプルではありませんが、拡張性と厳密なインタフェース定義を重視する場合には適した方法となります。
ERPと外部システム連携の具体例

ERPと外部システム連携は多岐に渡りますが、具体的な例は以下のとおりです。
- SFAとの連携
- ECとの連携
- 会計システムとの連携
- CRMシステムとの連携
順に解説していきます。
SFAとの連携
企業における営業活動の効率化と経営判断の迅速化を目的として、ERPとSFAを連携するケースが増えています。営業担当者がSFA上で管理する顧客情報や商談データをERPと統合することで、受注処理や請求業務がスムーズに行われ、業務の重複を防ぐことができます。これにより、営業担当者はより多くの時間を営業活動に集中できるようになります。
さらに、SFAで入力された営業データをERPに取り込むことで、売上予測やKPI分析の精度が向上します。これにより、企業は営業活動の効果をリアルタイムで把握し、より的確な経営判断を下すことが可能になります。
ECとの連携
ERPとECを連携することで、販売プロセスの効率化と在庫管理の精度向上が可能になります。例えば、ECサイトで発生した注文データをERPとリアルタイムで連携することで、受注処理の自動化が実現し、手作業による負担が軽減されます。
さらに、ERPとECの在庫データを統合することで、在庫の過不足を防ぎ、適切な在庫管理を維持できます。これにより、リアルタイムでの在庫状況を顧客に提供しながら販売が可能となり、機会損失の防止や売上の最大化につなげることができます。
会計システムとの連携
ERPの会計モジュールを利用しない企業や、既存の会計パッケージに慣れている企業は、外部の会計システムをERPと連携させる手段を検討することが多いです。
販売や購買などの取引データをERPで管理し、月次決算や支払処理は外部の会計システムで処理する形となります。
連携パターンとしては、1日数回バッチを回してファイルを取り込み、会計側に仕訳を自動生成する方式や、APIを利用してリアルタイム連携を行う方式などが考えられます。会計は企業にとって重要度が高いので、データの正確性とセキュリティをしっかり確保することが重要です。
CRMシステムとの連携
顧客管理や営業支援を行うCRMシステムとERPをつなぐことで、顧客情報・問い合わせ履歴・購買履歴などを多面的に活用しやすくなります。営業担当者が商談状況をCRMに入力すると、ERP側で販売予測や在庫計画に反映されるなど、部門横断で情報共有が可能です。
API連携でリアルタイムに更新するケースも多く、顧客ごとの購買パターンを即座に分析したり、経営陣がCRMデータをもとにERPでの利益シミュレーションを行ったりする利用シーンが広がっています。
ERPと外部システムを連携させる際のポイント

ERPと外部システム連携のメリットは大きい一方で、導入の手間やコスト、セキュリティ上の配慮も必要です。
とくに以下のようなポイントを押さえておくとERPと外部システムの連携がスムーズになるでしょう。
- インタフェースを調整する
- 開発に精通した人材を確保する
- データ連携ツールを活用する
- 強固なセキュリティを構築する
順に解説していきます。
インタフェースを調整する
ERP側と外部システム側でデータ項目や形式が異なることは珍しくありません。
インタフェースの仕様を整理し、どのデータをどのタイミングで交換するか、エラー発生時の処理はどうするかなどを明確に決めておく必要があります。
開発に精通した人材を確保する
APIやデータベース連携には専門知識・経験が不可欠です。
ERPベンダーや外部システムのサポートを受けるだけでなく、自社内に一定のエンジニアリソースを確保しておくと、運用開始後のトラブル対応や仕様追加にも柔軟に対応しやすくなります。
データ連携ツールを活用する
近年はiPaaSなど、異なるシステム間の連携を容易にするサービスが登場し、ドラッグ&ドロップでデータフローを構築できる場合もあります。
こうしたツールを活用すれば、ファイル転送やAPI接続の部分をテンプレート化し、開発工数を削減可能です。
強固なセキュリティを構築する
社外との通信を伴う場合はHTTPSやVPNを利用し、認証や暗号化を施すのが基本です。ERPは企業の機密データを扱うため、不用意に公開APIを設定すると攻撃者の標的になりかねません。
アクセス制御リストやファイアウォールの設定に加え、クライアント証明書や多要素認証などを検討する価値があるでしょう。
まとめ
本記事ではERPの概要や外部システム連携方法などについて解説しました。
ERPシステムは企業の基幹業務を一元化し、経営全体の効率化を支える重要なプラットフォームですが、その他にもさまざまな外部システムが存在します。SFAやEC、会計、CRMなどがその例であり、これらとERPを連携することでさらなる生産性向上やコスト削減が期待できるでしょう。
当社では、さまざまな企業へのERP導入実績があり、導入手順やポイントなどを熟知しております。ERPのことなら株式会社システムインテグレータにぜひ一度ご相談ください。
また、本記事だけでなくERPシステムをどのように検討すべきかより深く知りたい方に向けて、ERPの基本をまとめた資料も用意しています。お悩みの方は、こちらの資料もあわせてご覧ください。
- キーワード: