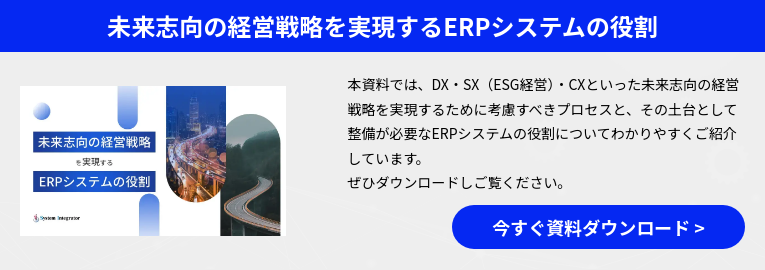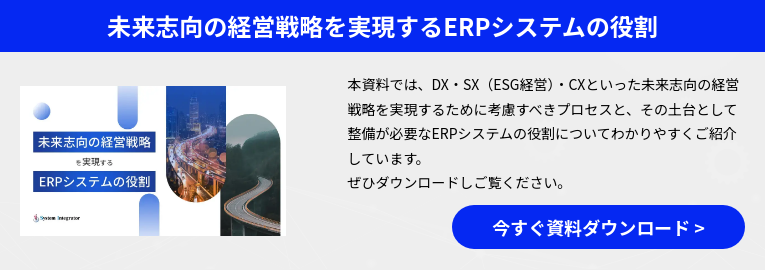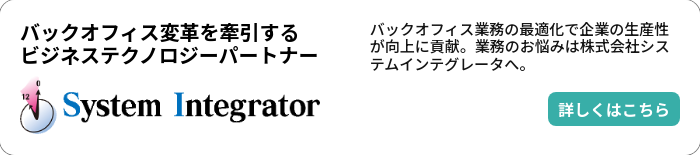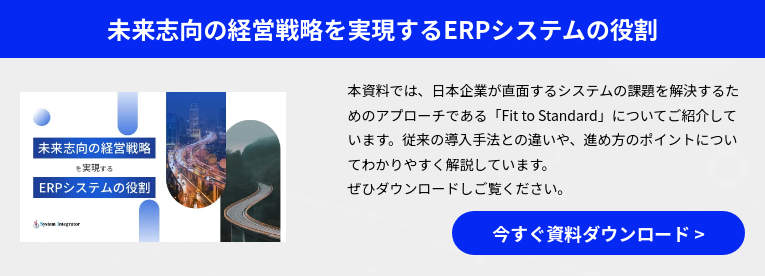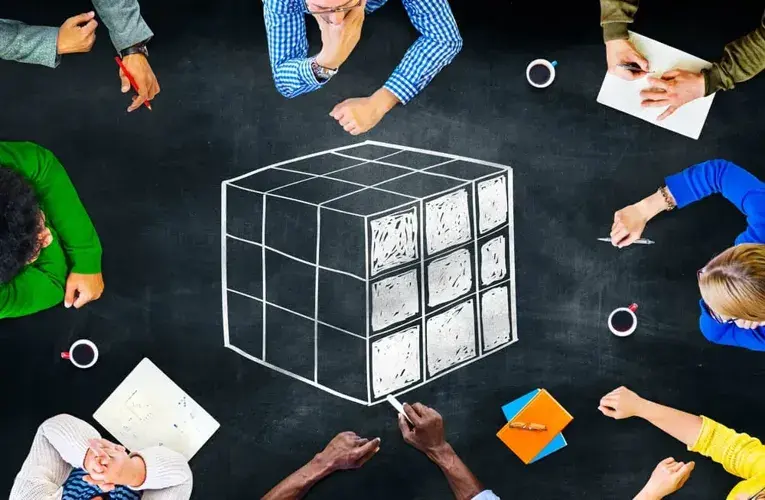何かと耳にする機会の多い 「DX」や「2025年の崖」。注目度が高まっているものの、まだきちんと理解できていないという方もいるのではないでしょうか。この二つのキーワードは密接に関係し合っていますが、実際に自分の言葉で説明するとなると難しいかもしれません。
そもそもDXとはどのようなもので、どのようなメリットがあるのか、疑問を持っている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、DXの概要やメリット・デメリット、DXの影響などについて解説します。
DXの定義・意味とは?
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、テクノロジーによって人々の暮らしをさまざまな視点から良い方向に変化させる取り組みのことです。
このDXには社会的な文脈における「広義」のDXと、ビジネスシーンにおける「狭義」のDXがあるため、それぞれご紹介します。
広義のDX
まずは広義のDXについてご紹介します。
そもそもDXとは、2004年にスウェーデンのウメオ大学教授であるエリック・ストルターマン氏が提唱した概念です。このなかでDXは「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」ものとして定義されています。
後述のビジネスシーンだけでなく、人々が生活する社会全体において、IT技術の進歩と浸透は良い影響をもたらすものである、という解釈ができます。
狭義のDX
一方、ビジネスに限定した場合のDXの定義は「デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること」とされています。これは、スイスのビジネススクールIMDの教授マイケル・ウェイド氏らの2019年の著書「DX実行戦略」にて紹介されました。
また、経済産業省も同年、DX推進ガイドライン(Ver. 1.0)を公開。その中でDXについて「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。
簡単にまとめると、狭義のDXは「企業が競争優位性を確立するためにビジネスモデルを変革する取り組み」であるといえます。
なぜ「DX」と表記するのか
英語では、DXを「Digital Transformation」と表記します。この「Trans」は「交差する」という意味があり、「cross(交差する、横切る、超える)」という単語と同義です。「cross」には十字に交差するという意味があることから、交差を一文字で表す「X」が用いられています。
ちなみに「DT」では、プログラミング用語であるHTMLの「dtタグ」と間違えやすいことも理由と言われていて、このことから官公庁やマスメディア、企業などでも「DX」という表記を利用しています。
デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い
DXと似た言葉に、「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」があります。それぞれどのような意味を持つのか説明します。
デジタイゼーション
経済産業省の定義によると、デジタイゼーションは「アナログ・物理データのデジタルデータ化」とされています。業務プロセスはそのままに、一部をデジタル化することによって効率化を図るものです。
例えば、
- 紙で管理していた顧客リストをSFAやCRMなどのシステムで管理すること
- RPAを使って業務の一部を自動化すること
などはデジタイゼーションに該当します。
このデジタイゼーションは、DXを推進する第一段階にあたります。DXでは組織全体をデジタル化していくことが必要とされるため、デジタイゼーションはあくまでもその一過程にすぎません。「DX=デジタイゼーション」と勘違いしてしまっている方も多いため、注意が必要です。
デジタライゼーション
こちらも経済産業省の定義によると、「個別の業務・製造プロセスのデジタル化」と明記されています。デジタイゼーションが情報のデジタル化であるのに対し、デジタライゼーションはビジネスのプロセスをデジタル化することです。
例えば、
- 自動車販売からカーシェアリングへ移行
- DVDのレンタルから動画配信サービスへの切り替え
など、デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革し、新たな顧客体験や事業価値を創造・提供することがデジタライゼーションに該当します。
さきほどデジタイゼーションがDXの第一段階とお伝えしましたが、このデジタライゼーションは第二段階であるといえます。ただし、デジタライゼーション=DXではありません。デジタライゼーションはビジネスモデルに対する変革を指しますが、DXが目指すのは組織全体の変革です。
DX推進過程の中で、デジタイゼーションが第一段階、デジタライゼーションは第二段階に位置しており、それらを経てDXが実現できるという構図について、正しく理解しておきましょう。
企業がDXに取り組むべき理由
近年注目度が高まっているDXですが、なぜ企業はDXに取り組むべきなのでしょうか。
その背景には「2025年の崖」への対策、そして変化の激しい市場環境への対応といった、日本企業が抱える課題があります。DXを推進できなければそれらの課題を解決できず、企業としての競争力を失ってしまう可能性すらあるのです。
以下にて詳しくご説明します。
「2025年の崖」への対策
「2025年の崖」という言葉をご存じでしょうか。この言葉とDXは深い関係にあります。
「2025年の崖」は経済産業省のレポートに登場した言葉で、日本企業におけるIT人材の不足と基幹システムの老朽化によって発生する問題のことです。「レガシーシステム」と呼ばれる時代遅れのシステムやソフトウェアを利用している企業はいまなお多く、システムを変えようにも実行可能なIT人材がいないことが問題視されています。また、その人材は既存システムの維持に精一杯になってしまっている状況です。
レガシーシステムは、業務に合わせたシステム構築や独自のカスタマイズを施されているものも多く、同じ環境を作り上げる難しさから、移行へ踏み切れないままでいる企業も少なくありません。しかしその分、システムの維持・管理には高額な管理費用がかかり、さらに老朽化によるセキュリティ問題なども発生します。
このようなリスクを負わないために、企業はレガシーシステムを脱却してDXに取り組むべきとされています。
ちなみに「2025年の崖」と呼ばれるようになった理由として、多くの企業で導入されていたERPシステムである「SAP」のサポート終了が、発表当初2025年に設定されていたことにあります。現在ではサポート終了が2027年まで引き延ばされましたが、サポートが終了するとアップデートが行われなくなるなど、さまざまな問題につながります。
「2025年の崖」については以下のブログでより詳しくご紹介しています。
「2025年の崖」とは?企業が直面する課題と克服に向けた道筋を解説
市場環境の変化への対応
近年、スマートフォンやインターネットが普及したことにより、消費者の需要や行動が著しく変わるようになりました。口コミやレビューが注目を集めることで、急に商品への需要が高まったり、売れなくなってしまったりと、急激な変化が発生するようになったのです。テクノロジーの進化による市場の急激な変化に対応できなければ、今後企業としての競争力をなくしてしまいます。
市場環境の変化に対応し競争力を得るためには、あらかじめ組織やビジネスの基盤をデジタル化させておき、環境の変化に柔軟に対応できる体制を整えておく必要があるのです。
このような点から、企業はできるだけ早くDXに取り組むのが望ましいでしょう。
DX推進のメリット
さまざまな企業がDX推進に取り組んでいる理由は、他にもたくさんあります。デジタル化による作業効率の向上はもちろん、働き方改革に役立ったり、思わぬアイデアから新商品が生まれたりすることもあるのです。
この項目では、DXを推進した際のメリットについてご紹介します。
生産性の向上やコスト削減
DXを進めることで、業務の生産性向上やコスト削減といった効果が期待できます。
デジタル化により業務を最適化したり、定型業務を自動化したりすることで、作業時間を減らし、人件費を抑えることができるでしょう。業務を自動化できればミスを減らすことにもつながります。
従業員がより生産性の高い業務に注力できるようになり、最終的に利益の向上といった効果も期待できるでしょう。
レガシーシステムからの脱却
先ほども触れたように、レガシーシステムから脱却できていない企業は少なくありません。古いシステムを使い続けていると、管理・維持に莫大なコストがかかってしまうだけでなく、扱える人材が減ることでシステムのブラックボックス化が起きる可能性も考えられます。また、古いシステムでは最新の市場環境に対応できず、企業としての競争力を失ってしまいかねません。
DXを推進してレガシーシステムから脱却できれば、維持管理にかかっていたコストを新たな投資に使えるほか、新しいシステムを活用することで市場環境に対応でき、競争力の維持・向上につながります。
新規サービスの創出
デジタル活用によって新規サービスが生まれることもあります。例えば、業務のデジタル化を通じて顧客のニーズや生の声が届きやすくなれば、製品開発のヒントも増えるでしょう。また、既存のサービスやプロダクトがデジタル化されることによって、新たな形のサービスとして生まれ変わる可能性もあります。
ちなみに、近年の傾向として「所有」よりも「利用」に需要があり、それを予測したさまざまな企業がサブスクリプション型のサービスを提供するようになりました。こういった予測においても、DXは必要です。
働き方改革
近年、場所を選ばない働き方である「リモートワーク」が普及しています。デジタルを通じて、場所や環境に縛られない働き方はこれからも広まっていくと予想されますが、これもDXのメリットです。
これは、仕事をプロセスよりも成果で評価する時代が来る、ということでもあります。そうなると、仕事単位で従業員を雇うといった形式が増えていくことも考えられます。以前よりも多角的な働き方が求められるようになるでしょう。
BCPの充実
BCPとは、事業継続計画のことです。「テロや災害、システム障害など危機的状況下に置かれた場合でも、重要な業務が継続できる方策を用意し、生き延びられるようにしておくための計画」のことを表しています。
文字通り、災害の被害にあった場合でも、テレワークの体制が整っていれば安心して働くことが可能です。新型コロナウイルス感染症の流行が始まり、テレワークへの切り替えを求められた際に、テレワーク化が可能な業種にも関わらず対応できない企業があったことは、「BCPの遅れ」の典型的な例と言えるでしょう。
このような働き方へのIT投資もDXを進めるうえでは重要です。
DX推進のデメリット
さて、ここまで紹介したように、効率的な働き方を実現するためにはDXは欠かせません。
一方で、DXの取り組みを始めるためにはいくつか注意点もあります。この項目では、DX推進のデメリットと対策をご紹介します。
初期費用が大きい
DXのデメリットとして「導入・実現にかかるコストが大きい」というポイントが挙げられます。
レガシーシステムから脱却するには時間もかかり、システムの選定などの準備や従業員への説明など、やるべきことも山積みです。また、自社の業態に合わせるためには、追加の機能開発が必要な場合などもあるでしょう。自社の業務にマッチするようにシステムをカスタマイズしていく過程で、結果的に費用がかさんでしまうケースも珍しくありません。
こうしたトラブルを回避するためには、あらかじめ自社の課題点とワークフローを明確にすること、そしてその課題解決に活用できるシステムの特性を理解しておくことが大切です。
例えば、オンプレミス型のサービスはカスタマイズ性・セキュリティ性能に優れる一方、導入費用は高くつきがちです。一方、クラウド型のサブスクリプションサービスなどは定額制であることが多く、初期費用を軽減できます。また、SaaS・PaaS・IaaSなど活用するシステムのジャンルによっても開発に関わる金額は変化します。
こうした種別ごとの特性をよく理解しておくことで、無駄なランニングコストを回避することができるでしょう。
効果が出るまでに時間がかかる
DXはすぐに効果が出るものではありません。
単なる業務のデジタル化のみであればすぐに成果が見えてくるものですが、DXはビジネスモデルや組織そのものを変革させていくため、効果が出るまでに年単位で時間がかかります。
そして、さきほど紹介した初期費用だけでなく、取り組みを進めている間は常に人材やシステム・ツールなどにランニングコストがかかり続けます。
そのため、DXを実現するためには、あらかじめ長期的な視野で計画を立て、十分な資金やリソースを用意しておく必要があります。
改革への反発が起きる可能性がある
DXには社内全体の協力が必要です。しかし、DXは組織全体に大きな変革を求めることになるため、変化を拒む従業員も出てくるでしょう。
デジタル化についていくのが不安という声や、これまでのやり方を否定されたと考えて反発する声、コストがかかる割に効果が見込めないのではないかという不安の声が出る可能性もあります。
この状況を打開するためには、「なぜDXを行う必要があるのか」「DXによって得られるメリット」などを従業員に理解してもらう必要があります。DXへの理解を深めてもらうための活動や、経営層がDXに強くコミットして従業員を引っ張っていくなど、DXが企業の重要な戦略として位置づけられていることを伝えていかなければなりません。
DXを取り巻く技術
インターネットやシステムを業務で使うことがDXではありません。
経費精算が紙からシステム変わると確かに作業効率は上がるのですが、ビジネスの変革かというならば、そうではありません。
Windows95の登場以降、IT企業に限らず誰もがPCをビジネスで利用するようになりました。インターネットの登場も同時期ですし、業務を効率化するためのソフトウェアは昔からあります。
PCもインターネットもDXにおいて欠かせない技術要素ではあるのですが、指数関数的にビジネスを拡張させる以下の技術に注目が集まっています。
5G
5Gとは、第5世代移動通信システム(5th Generation)のことです。これまでの4Gよりも通信速度も同時接続性も高くなり、遅延も少なくなることから、機械、物、デバイスの接続性についても向上させるメリットがあるとされ、後述するIoTの活用において欠かせない技術です。
IoT
IoTとはInternet of Thingの略称で、モノのインターネットのことです。機械をネットワークに接続することにより、遠隔操作したり、膨大なデジタルデータをリアルタイムに収集したりすることができるようになります。膨大な機械のデータを処理し、活用するために後述するAIが欠かせません。
AI
AIとはArtificial Intelligenceの略で人工知能のことです。機械学習やディープラーニングという手法を活用し、膨大なデータを学習させることで、目的に沿った結果や判断を導くことができます。分析や予測に活用するだけでなく、自動運転や翻訳、音声アシスタントなど幅広い領域で活用されています。
この5GとIoTとAIの活用による新たなビジネスモデルは、その技術的特徴や限界費用がゼロに近くなることから指数関数的な成長を期待することができると言われています。
もちろん市場が指数関数的に伸びていくかというならばそれは違うので、ビジネス戦略との整合性が求められます。
DXを推進する人材
DXを進めるうえで、部門に縛られず全社的に動くことができる人が必要だと解説しました。
では、実際はどういった人材が求められているのでしょうか。
経済産業省のDXガイドラインによると「DX 推進部門におけるデジタル技術やデータ活用に精通した人材」「各事業部門において、業務内容に精通しつつ、デジタルで何ができるかを理解し、DXの取組をリードする人材」となっています。
つまり、DXについて理解しているシステム部門の人材のみでは成り立たず、各部門の業務をよく理解している人物がDXを進める必要があるのです。
ここからは、一般的にDX人材と呼ばれる職種をご紹介します。
ビジネスプロデューサー
ビジネスを創造する指導者のことです。豊かな発想力と、異なる価値観や才能あふれる専門分野の人たちを関連づけて調整する力が求められます。
ビジネスデザイナー
製品やサービスを、ビジネスとして成立させるための仕組みを構築する人です。
事業推進計画書の作成し、事業を構築していくスキルが求められます。
アーキテクト
全般的な構造の設計や、基礎・中核部分の設計や仕様策定、全体のプロジェクト管理などを担当する技術者です。IPA(情報処理推進機構)が提供している国家資格に「システムアーキテクト試験(SA)」があります。
データサイエンティスト
データ収集や分析などの観点から合理的判断をサポートする人です。データを可視化するスキルや機械学習などのスキルが求められます。
UXデザイナー
ユーザーのニーズ分析やサービス・プロダクトの目的・目標の設計を担当する人です。ブランディングや開発に関する知識などが求められます。
エンジニア
工学(エンジニアリング)に関する専門的な知識やスキルを持った人です。コンピューターの仕組みやプログラミングへの関心が高く、常に最新の情報や技術を取り込む力が求められます。
DXの推進事例
ここからは、実際にDXを進めた企業の事例を見ていきましょう。
DX推進で売上3倍を実現
まず、老舗の看板屋を運営するクレストホールディングス株式会社のDX推進事例を紹介します。
クレストホールディングス株式会社は、需要の減少に悩まされるレガシー産業のひとつでした。そうしたレガシー企業の現状を打破するため、DX推進として実践したのが以下の2ステップです。
- デジタルトランスフォーメーションによる組織や事業の生産性の向上
- レガシーアセット ✕ ITによるイノベーションで新しい価値の創造
代表取締役社長の永井俊輔氏は、業界としての認知度の低さや、組織として機能していない現状に危機感を覚え、DXを進めました。最初に推進した内容は、以下の通りです。
- サプライチェーンの変革
- あらゆる領域にITツールを導入し効率化を徹底
- 組織編成を機能別にし役割を明確化
- KGIの分析やKPIの設定を週次で実践
- 組織内に評価制度を導入
こうした取り組みを経て、次のイノベーションを起こすステップへと進んでいきました。看板事業の課題に正面から向き合い、Web広告の計測を参考にした効果測定を実施。投資の最適化を顧客に提案しました。この取り組みにより、クレストホールディングス株式会社は売り上げを5年で3倍にまで上げるなど大きな成果を実現しています。
レガシー産業からの脱却。老舗の看板屋がおよそ「5年で売上3倍」を実現した改革の全貌
DX推進でコスト削減を実現
DX推進は売上向上だけでなく、コスト削減の実現にも繋がる場合もあります。建機・農機などの製品を通じたトータルソリューションの提供をするグローバル企業・クボタのDX事例を見ていきましょう。
グローバル企業として、海外にも多くの販売子会社を抱えているクボタは、建機の修理対応が課題でした。多くの修理対応を現地販売店のサービスエンジニアが行うため、マニュアルだけでは十分な対応ができません。ダウンタイムで建機が稼働できず、ユーザーの収益率低下につながるケースもあり、早急な対策が必要でした。
また、従来の修理は建機のマニュアルの中から該当する箇所をわざわざ見つけ出して対応していたため、手間も問題視されていました。クボタはこうした課題に直面し、DXを推進したのです。
まず、クボタは販売代理店のサービスエンジニアを対象に、ARや3Dモデルを活用した故障診断アプリ「Kubota Diagnostics」を提供。このアプリにより、建機が故障した際のダウンタイムが軽減されました。ダウンタイムの軽減で顧客側のコスト削減に貢献し、カスタマーサポートの業務効率化も同時に実現しています。
そしてDXを推進するうえで、クボタは故障診断フローのデジタライズと、エンドユーザー側が故障箇所を特定できる仕組みの構築を行いました。実際に導入された対策を以下に挙げます。
- エラーコードや不具合症状を入力し、修理方法や点検箇所が自動で表示されるフローの構築
- スマートフォンをかざすだけで故障箇所や部品を特定できる故障診断機能を搭載(3Dモデル・AR)
- 現地ユーザーに向けて日本語マニュアルを英語圏用に再構築(米国ユーザーに向けたトレンドの取り入れなど)
- マルチデバイスへ対応可能な「Flutter」を採用して独自のCMSを構築(故障余地や診断フローの整備の実現)
こうした対策を取り入れた結果、企業にはさまざまな変化が起こりました。特に、3Dモデル・ARによる故障診断機能が注目され大きな話題になり、日本を始め世界への順次展開と対象機器の拡充が期待されました。
そして、人員の確保やサービスエンジニアの教育といった側面にも好影響を与えています。また、クボタは故障診断フローの精度向上や、機能拡充に向けて継続したローカライズ支援を世界各地へ行う計画も発表しています。
3Dモデル・ARを活用した診断を提供し、建機故障時のダウンタイムを低減
DX推進で口座開設者数2倍を実現
DXの推進で好影響が出た事例として、金融業であるSMBC信託銀行の取り組みを紹介します。
SMBC信託銀行のDXは、2019年10月に「GLOBAL PASS」という多通貨Visaデビット一体型キャッシュカードのリリースに合わせて、効果的な訴求のためにオンライン中心のマーケティングを展開したことがきっかけです。
主なアプローチとしてはYouTubeでの広告配信を始め、ポータルサイトや会員向けのEメール配信などが行われました。
また、海外現地での決済やATM利用などを外貨のまま取引可能にした取り組みも評価されています。このような手法の展開により、オンラインを経由した既存顧客のGLOBAL PASSへの誘導が成功し、新規での口座開設者数をこれまでの2倍に増加しました。
金融機関3社のDX事例、SMBC信託・アクサ生命・みずほFGはどうやって成果を出したか
DX推進における課題とは?
DX推進における成功例をご紹介しましたが、全ての企業がDXに積極的に取り組み、成功を収めているわけではありません。ここではDX推進に当たって現在どのような課題があるのかについて解説します。
ITリテラシーの低さ
ITリテラシーとは情報技術を使いこなす力のことで、公のものとしては厚生労働省が2017年に発表した平成29年度ITリテラシーの習得カリキュラムに関する調査研究報告書があります。この報告書では、基礎的ITリテラシーを以下のように定義しています。
「現在入手・利用可能なITを使いこなして、企業・業務の生産性向上やビジネスチャンスの創出・拡大に結び付けるのに必要な土台となる能力のこと。いわゆるIT企業で働く者だけでなく、ITを活用する企業(ITのユーザー企業)で働く者を含め、全てのビジネスパーソンが今後標準的に装備することを期待されるもの」
つまり、世の中のITの機能や仕組みを理解し、どのような場面で活用されているか知っている人、あるいは業務における問題に対して、活用できるITを選び安全に操作することができる人を、ITリテラシーがある人と言うのです。FAXでのやりとりや印鑑による承認など、紙に頼った業務がまだまだ多い日本では高いITリテラシーをもった人材が求められています。
人手不足の深刻化
人材不足のために、DX推進に苦戦している企業が多い現状は軽視できません。
IT人材の慢性的な枯渇により、経済産業省からは「2030年には約45万人が不足する」という見通しが立っています。DX推進にはエンジニアを始め、イノーベーターやビジネスデザインのできる人材が欠かせません。
しかし、こうした人材はITベンダー企業に偏ってしまい、多くの企業で人材不足が深刻化しています。そして、人材不足が影響してIT人材確保の競争も今後ますます激化していくでしょう。
従って、関連企業ではDX推進のための人材確保や育成を早急に進める必要があります。
レガシーシステムの影響
DXを推進させるうえで、レガシーシステムが「技術的負債の塊」として取り上げられています。
経済産業省によれば、IT予算のおよそ9割が老朽化システムの維持にコストを割いているとのデータが掲示されています。また、8割の企業で老朽システムの残存が報告されています。攻めのIT投資の傾向が強いアメリカと比較しても、日本は守りのIT投資と表現されるほど保守的です。
こうした背景からも、レガシーシステムを一変させ、IT予算を戦略的に投資することがDX推進のポイントです。
一貫性のないシステム
ITシステムの課題として、システムの一貫性が挙げられます。多くの企業で、システムの開発や改善を短期で行っている影響から、システムのブラックボックス化や保守運用費の高騰化が問題視されています。
一貫性のない複雑なシステムはIT人材や管理維持する際に負担となる要素のため、見直しを迫られている企業は少なくありません。早急にDXを推進し、技術的負債の老朽システムを改善していきましょう。
DX推進を成功させるためには?
企業でDX推進を成功させるには、社内全体の足並みを揃えることも大切です。事業部それぞれで率先して協力し合うことはもちろん、経営陣のコミットメントも大切です。DXで生み出すべき価値や変革の方法、予算や人材の割り当てなど、現場と確実な意思疎通を図ったうえで社内全体の方向を決めていきましょう。
そして、社内で固めた方針を実現させるためには、DX推進に対応できる人材の確保と育成を優先して行うことも大切です。そして、DX推進メンバーを適切に配置することも重要でしょう。また、技術的負債となっているレガシーシステムの一新も、DXを推進するうえで避けては通れません。そのためには、全体を俯瞰した一貫性のあるシステムを構築する必要があるのです。一貫性のあるシステム構築を行えば、全体を通したシームレスなデータ活用が実現可能になり、競争力向上や効率化が期待できるでしょう。
ただし、社内全体の足並みを揃えることは比較的容易ですが、人材確保・育成や一貫性のあるシステム構築には時間やお金がかかります。従って、DXの推進には中長期的な目線が必要です。企業競争に乗り遅れないために、中長期のプロジェクトになると認識したうえで、早急にDXに取り組んでいくべきでしょう。
バックオフィス業務改善ならシステムインテグレータ
多くの企業で人手不足が大きな課題となっていますが、バックオフィス業務にはいまだに属人化した作業やアナログ業務が残っており、企業の成長と発展を阻む大きな壁となっています。
バックオフィスの業務プロセスを最適化することで、コスト削減や属人化の防止だけでなく企業全体の生産性向上にもつながります。
当社はERPをはじめとする情報システムの豊富な導入実績をもとに、お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適な改善策を提案します。業務の洗い出しや問題点の整理など、導入前の課題整理からお手伝いさせていただきます。
バックオフィス業務にお悩みをお持ちの方は、お気軽に株式会社システムインテグレータまでご連絡ください。
まとめ
DXとは、デジタルを活用した変革のことです。広義では「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」という意味で使われています。一方、ビジネスに限定した場合のDXの定義は「デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること」となります。デジタイゼーションやデジタライゼーションとは異なり、デジタル化と活用の先を見ているのがDXの特徴と言えます。
「2025年の崖」問題の解決や、変化が目まぐるしい市場環境への対応が求められている多くの企業において、DXは取り組むべき大きな課題だと言えるでしょう。
生産性の向上や新規サービスの創出、レガシーシステムからの脱却といったメリットは企業に大きな影響をもたらします。初期費用や効果に時間がかかるなどのデメリットは、対策をとって地道に進めていくことで回避できるものや軽減できるものもあるため、DX推進人材の担当者たちと力を合わせて進めていきましょう。