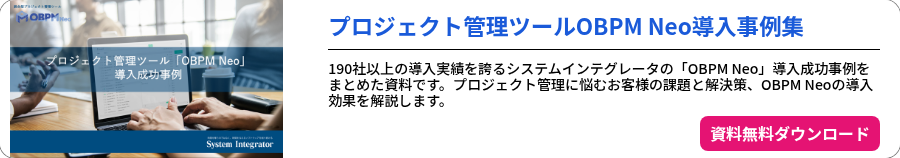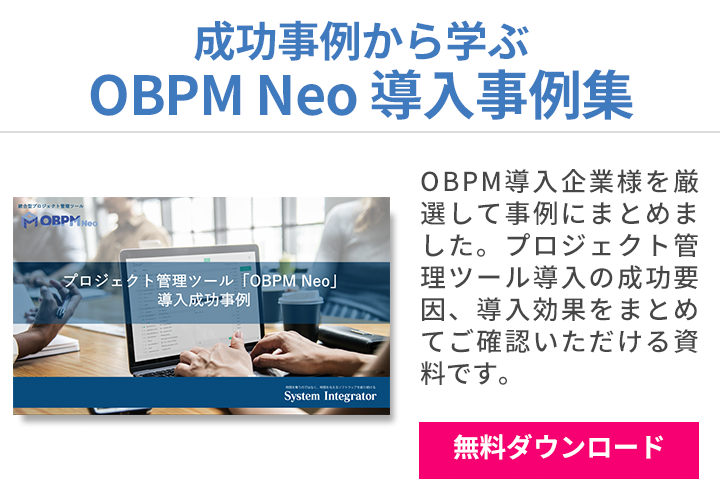導入事例インタビュー:株式会社YE DIGITAL様

自社開発プロセス一新に伴い「OBPM Neo」を導入
コスト管理や標準ルールの運用を実現

常務執行役員 業務改革本部長 石田 聡子 氏(写真:中央)
業務改革本部 情報化推進部 情報化推進担当課長 桑野 直美 氏(写真:左)
業務改革本部 情報化推進部 副部長 伊東 仁 氏(写真:右)
| 事例のポイント |
|---|
|
YE DIGITALについて
1978年に安川電機のIT部門から分社化して設立された株式会社YE DIGITAL。創業以来、日々進化する技術を積極的に取り入れながら、お客様の課題解決に一緒に取り組んできた会社です。
「デジタルで、暮らしに明るい変革を。」というスローガンのもと、IoTやAIなどの先進技術による業界特化型システムの構築やITシステムの受託開発、カスタマイズ等お客様の業務改善と経営革新を支援しています。
抱えていた課題

-「OBPM Neo」導入前に、抱えられていた課題を教えてください。
伊東氏:自社開発した既存システムの老朽化が課題でした。
コスト管理、勤怠等、システム・ツールが分散しておりプロジェクトとして情報が統合されておらず、情報が“たこつぼ化”され、プロジェクトの統合的な状況把握・分析が難しい状況でした。
石田氏:DXを推進する上で、自社で開発した日報入力とオーダー原価の予実管理には限界がありました。プロジェクト途上でのスケジュール遅延やリスクが見えないことや、自社でのメンテナンスコストも大きく、先進的な管理手法を吸収・反映するところまでは至っていない状態でした。
社内の優秀な開発メンバーは外の仕事で忙しいため、せっかくシステムを切り替えるなら、業界で一番いいものを使うことで、仕事のやり方を見直し生産性を高めることができるSaaS型のクラウドサービスを導入する必要がありました。
課題解決のために
- 導入のきっかけ、選定したポイントを教えてください。
伊東氏:シェアの高いプロジェクト管理ツールを調査し、いくつか候補がありました。その中で、「OBPM Neo」が一番既存の業務運用とのギャップが少なく、特にコスト管理の運用が社内のルールと近しかったことがポイントでした。
そもそもコスト管理ができないツールや、運用手法が合わないツールもある中で、「OBPM Neo」ならばメンバーにもスムーズに受け入れられるのではと思いました。
石田氏:社内での承認を得る上で、「OBPM Neo」がプロジェクトマネジメントの世界標準である「PMBOK」に準拠して作られたサービスであることは大きなアピールポイントでした。
また、「原価(コスト)管理」ができること、保守の観点から国産であること、既存の運用に適していることなども「OBPM Neo」を選定したポイントでした。
導入にあたって
- 導入決定から稼働までのお話をお聞かせください。
伊東氏:どこの会社、ツールでも一緒かと思いますが、初期のツールの使い方レクチャーは苦労しました。従来の自社開発システムは多くの独自カスタマイズがされていたので、比較されることもありました。「OBPM Neoではこう対応する」というのを利用部門と調整し、運用ルールを決めていきました。
桑野氏:いまだに各事業に特化した使い方はできないのか、などのピンポイントな要望はありますが、標準化したルールを元に運用するように指示しています。
まずは各事業部ごとのキーマンにレクチャーし、チームに浸透させてもらうというように組織面でも工夫しています。
石田氏: ツール選定の期間を設け、技術部門によるトライアル・課題のヒアリングを実施、本当に現場で使えるかという議論を繰り返し行い、全社統一に至りました。
導入後も1年強の移行期間を設け、経営会議等で移行計画を示しながら、優先度の高い大口オーダーから順次移行しました。
アジャイルの時はこのように管理する、など各ケース別のドメイン(雛形)を用意したり、運用上の課題・疑問について、部門リーダーを集めて運用方法をガイドしたり、3年経った今も少しずつ「OBPM Neo」を浸透させていっている最中です。
見えてきた効果
- 実際の導入効果についてお聞かせください。
伊東氏:シンプルにSaaSでどこにいても利用できることがメリットです。
経営層への重点プロジェクト報告が「うまくいってます」の一言など定性的なものだったのが、「OBPM Neo」のデータによる定量的な報告に変化しました。いずれ会議は「OBPM Neo」の数字ベースで必要なプロジェクトのみ報告するというスタイルにしていきたいです。
また、ドメインマスタによる雛形運用を本格化しました。成功プロジェクトからドメインマスタに管理内容を取り込み、随時雛形をアップデートしています。
ツール導入により品質管理の適用範囲を広げ、小規模オーダーを含めるようにしました。統合的に管理することで、より細部もマネジメントすることが可能になりました。
石田氏:事業別の雛形登録や、開発実行計画作成、デザインレビュー、週次のオーダー進捗作成を「OBPM Neo」をベースに移行し、全社の規程に沿ったプロジェクト管理が「OBPM Neo」でできるようになりました。
すべてのオーダーは「OBPM Neo」で管理する、小口オーダーではガントチャートのタスクの細分化は免除、10万円以上のオーダーは「OBPM Neo」から抽出したレポートを使ってプロジェクト進捗を経営会議で報告、などルールを定め運用しています。
また、正しく計画・実績が入力されると、要員計画の進捗率と作業の進捗率の差からプロジェクトの遅れがデータで把握できるようになりました。
今後も不採算プロジェクトのリスク早期検知を目標に、データ入力の徹底を浸透させていきます。
今後「OBPM Neo」に期待すること
- 弊社に対するご要望などあればお聞かせください。
伊東氏:実運用に合わせ、「工数実績入力集計の方法=当日までの集計方法」への変換やドメインマスタの変更・適用の簡易化、拡充、スケジュール変更の簡易化、自動変更など細かい要望はいくつかあります。
また、AIがプロジェクトに関してアドバイスをしてくれるような機能があればぜひ利用したいです。
開発手法の変化や、PMBOKに合わせたツールのアップデートに期待しております。
石田氏:そうですね、AIがアドバイスしてくれる機能があれば嬉しいです。自社の知見だけではなく、一般的な過去の定石から第三者の立場として指摘を受けられたら良いですね。
運用面では、プロジェクトリスクを「OBPM Neo」データのみで漏れなく検知するためのノウハウが知りたいです。どうすれば正確な数字を入力してもらえるか、今後ご相談させてください。
また、開発生産性向上のために、開発手法も日々変化していきますが、それに対応したプロジェクト管理がきちんとできるか、そちらも今後期待しております。
桑野氏:パートナーが外部から「OBPM Neo」に数字を入力するケースが増えてきており、セキュリティ面での配慮がより重要視されております。セキュリティ面に関わるアップデートを今後も強化していただきたいです。

今後もより使いやすいパッケージをご提供できるように努力してまいります。
貴重なご意見ありがとうございました。

株式会社YE DIGITAL
プロジェクト管理ツール:OBPM導入事例集