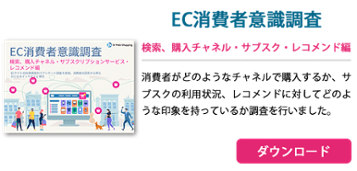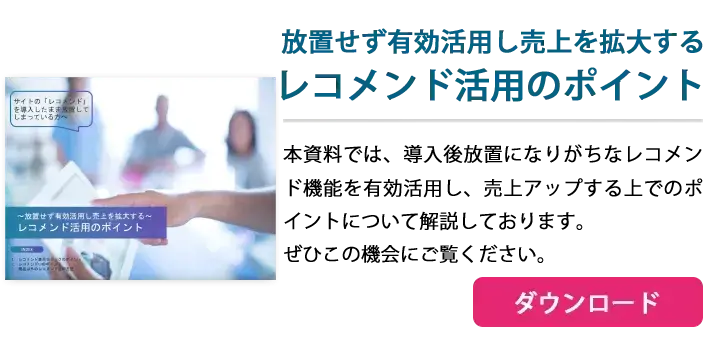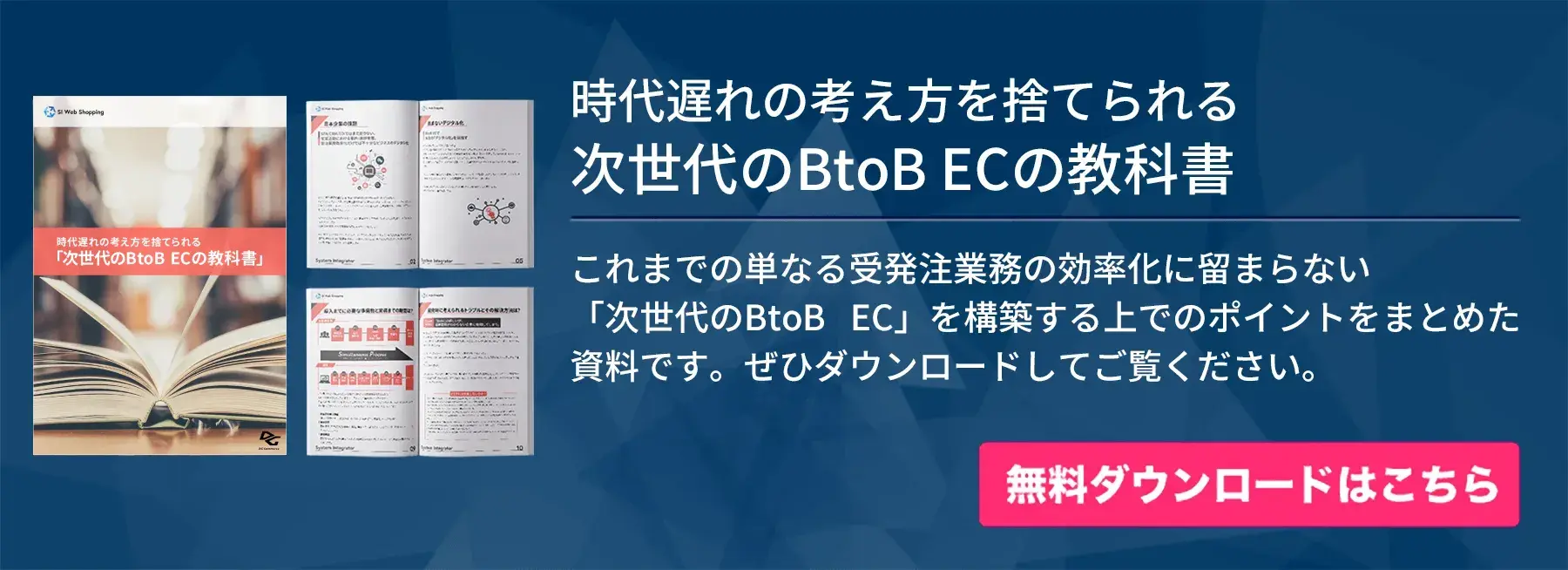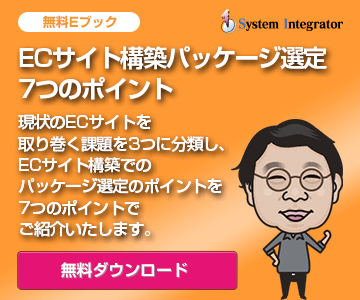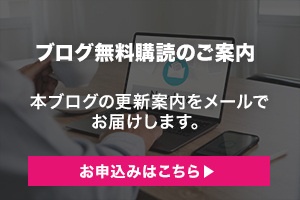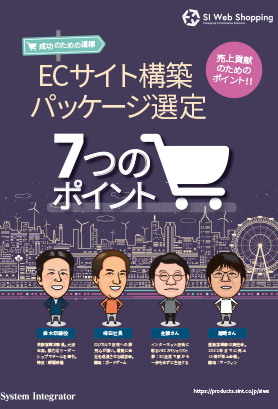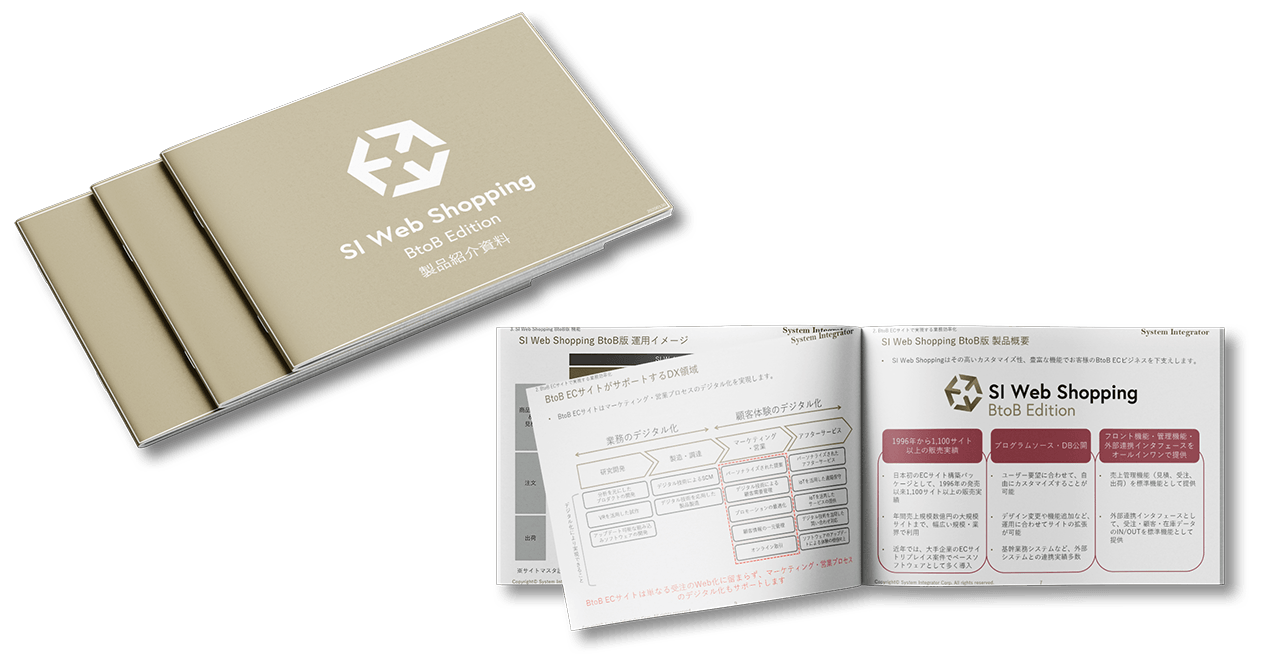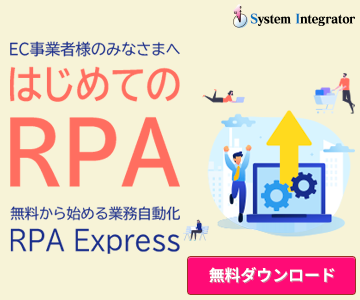企業が消費者に商品・サービスを販売するBtoCビジネスにおいてECサイトの活用事例が増えていることは周知の事実ですが、近年では企業間取引であるBtoBビジネスにおいてもECサイトの導入が進められています。
ビジネスの成長・存続・拡大のためにBtoB-ECの導入を検討している方も多いのではないでしょうか。当記事では、BtoB-ECの概要や現況、導入メリット、成功事例についてご紹介しています。
成功事例を数多く参考にすることで、ビジネス推進のヒントや役立つ情報を効率的に得ることができます。BtoB-ECの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
BtoB ECとは

BtoB-ECとは、BtoB(Business to Business・企業間取引)をEC(electronic commerce・電子商取引)で行うことです。つまり、従来のアナログな取引方法ではなく、デジタル化された商取引を行うことを言います。
BtoB-ECは、商品カタログに記載されているような、標準化された規格・商品・サービスの取引に活用されることが多くあります。
オンライン上で取引が行われるBtoB-ECは、従来のアナログな取引よりも利便性が高くスピーディーな取引を行えることから、多くの企業で導入が進められています。
BtoB-EC特有の機能については、以下の記事でご紹介しています。実際に利用される機能を把握することで、BtoB-ECへの理解も深めることができるため、ぜひご参考下さい。
BtoB ECの特徴とその他のECとの違い
BtoB-EC以外にも、BtoC-ECやCtoC-ECといったさまざまなタイプのECが存在します。各形態の違いについて以下にまとめました。
|
形態 |
取引対象 |
|---|---|
|
BtoB-EC |
企業対企業 |
|
BtoC-EC |
企業対個人 |
|
CtoC-EC |
個人対個人 |
各形態での主な違いは、取引の対象となる相手です。BtoB-ECにおいては、メーカーとサプライヤー、卸売業者と小売業者といった企業間・法人間の取引が行われます。
当然ながら取引対象が違うことから、取り扱う商材の特性や単価、マーケティング手法やビジネスプロセスにも違いが出てきます。
BtoB-ECとBtoC-ECの違いについては、以下の記事で詳しく解説しているため、併せてご参考下さい。
BtoB ECの市場は拡大を続けている
経済産業省の調査報告書によると、BtoB-EC市場は年々拡大を続けており、2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で市場規模が一時的に低下したものの、334兆円という強大な市場を形成しています。EC化率については33.5%という数字を記録しています。

出典:経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)
このようにBtoB-ECが拡大した背景には、次のような理由が考えられます。
働き方改革の推進
働き方改革が目指す長時間労働・生産性向上を実現する手段としてBtoB-ECを導入する企業が増えた。
BtoB-ECを活用する環境が整った
ITツールの発展やインフラ整備が進んだことにより、BtoB-ECを活用する環境が整った。
低コストでの導入が可能となった
BtoB-ECの普及が進んだことにより、さまざまなパッケージやクラウドシステムが登場。独自システムを構築せずともBtoB-ECを導入することが可能となった。
BtoB ECの導入成功事例

BtoB-ECのノウハウや成功のポイントを学ぶには、実際にBtoB-ECの導入に成功した企業の事例を参考にすることがおすすめです。実践的で活きた情報が手に入るため、これから導入を検討している方は、導入をスムーズに行ったり成功確度を高めたりといった効果が期待できます。
以下に、BtoB-ECの導入成功事例を厳選して4例ご紹介していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
ミスミ
BtoB-ECサイト「MiSuMi-VONA」を運営する株式会社ミスミグループは、本来金型用精密機械部品を「高品質・低コスト・短納期」で提供することで圧倒的シェアを獲得してきた商社です。
2010年より自社製品だけでなく他社製品も取り扱うこととなり、新たな販路としてBtoB-ECサイトを開設。「高品質・低コスト・短納期」というコンセプトはそのままに、取扱商品点数・ラインナップを拡大して現在では1,500メーカー・900万点という業界トップクラス規模・売上高を誇るBtoB-ECサイトへと成長しています。
コンセプトを崩さずにビジネスの規模を拡大している点や、膨大な商品点数を素早く探せるシステムなどは、これからBtoB-ECに取り組む方の良いお手本となるのではないでしょうか。
モノタロウ
株式会社MonotaROが運営するBtoB-ECサイト「モノタロウ」は、1,800万点以上の商品点数を誇る工業用関節資材通販サイトです。膨大な商品点数・出荷スピードの速さなどから通称「工場のAmazon」と呼ばれています。
かつての工業用関節資材業界は、業者への問い合わせやカタログ注文が一般的であり、注文個数による価格変動もあったため、小口発注を行う中小企業は単価が高く納品も遅くなる課題を抱えていました。
モノタロウが成功したポイントは、BtoB-ECに取り組むことで、充実した品ぞろえ・1点からの発注・当日出荷など小規模事業者にも利用しやすいサービスを提供したことです。商品名・品番での検索や多様な決済方法の整備により、誰にでも使いやすいECサイトを構築したことも、同サイトが支持されているポイントと言えます。
現在では、工業用関節資材の流通を効率化したパイオニアとして多方面から支持されており、販売実績・知名度ともに成功を収めています。
熊本馬刺しドットコム
食品通販事業「熊本馬刺しドットコム」を営む株式会社利他フーズは、BtoB・BtoCの切り分けができていないため最適な施策が打てないことや、BtoBの掛け払いに時間がかかること、業務効率が悪いことに課題を抱えていました。
BtoBの販売促進・業務効率化のためにBtoB-ECを導入したところ、BtoB・BtoCの切り分けが可能となり飲食事業を営む店舗向けの施策が打てるようになったことで、毎月100店舗の新規獲得や受注単価アップを実現。BtoB特有の掛け払いもシステムで自動化され、販売促進やより重要な業務に使える時間も増えました。
BtoB-EC導入後の同社は、営業スタッフによる新規開拓無しで売上倍増という驚きの成果を達成しています。BtoB・BtoCが混在したECを運営しており、販売促進や業務効率に課題を抱えている方は、専用のBtoB-EC導入を検討する際の良いモデルケースとなるのではないでしょうか。
ニトムズ
ニトムズは、株式会社ニトムズが運営する清掃用具・衛生用品・文房具といった企業向け日用品や衣料製品を販売するBtoB-ECサイトです。取扱商品は24時間365日、ロット数によらず注文可能という利便性の高さで人気を集めています。
同社がBtoB-ECサイトを導入したきっかけは、新事業として立ち上げた自社ブランドの販路開拓でした。後発組であるため従来の提案営業スタイルでは販促や他社との差別化が難しく、小売店が気軽に商品を仕入れることができる仕組みの提供・自社の販路開拓としてBtoB-ECの導入に踏み切ったそうです。
BtoB-ECサイトの開設以来、多くの文房具小売店・インテリア雑貨店が登録を行い、目論見通り新たな販路として機能しています。
BtoB ECを導入するメリット

多くの企業がBtoB-ECに注目している理由は、ビジネスを推進していくうえで多くのメリットがあるためです。近年では企業間競争の激化やビジネスモデルの高度化・複雑化により、自社のビジネスを成長させるためにBtoB-ECを実際に導入する企業も増え続けています。
ここでは、BtoB-EC導入により得られる主なメリットについてご紹介します。
業務負荷の軽減
従来のBtoB取引では、電話・メール・FAX等で顧客からの発注を受け付け、担当者が都度業務システムに入力を行う必要があるため、業務が非常に煩雑で労力がかかります。
BtoB-ECを導入すれば、受注がシステム化されることで手作業での受注処理や入力業務を大幅に削減することができます。また、顧客はオンライン上で商品情報・受発注履歴・在庫情報の確認を行うことができるため、受発注に伴う問い合わせ対応も大幅に削減することが可能です。
電話注文による聞き間違いや、手作業での確認や入力で発生する誤入力といったミスも削減でき。確認や修正の労力も削減できるでしょう。
このように、取引に要する業務負荷を大幅に軽減できることが、BtoB-ECを導入する大きなメリットのひとつです。
マーケティング強化につながる
BtoB-ECを導入すれば、売上・販売数・リピート率・利用状況といった取引データを蓄積できるため、データを分析して改善を行うことで、マーケティング施策に活かすことができます。また、ECシステムから顧客に対してキャンペーン・限定販売・カタログ掲載といった販促施策を行うこともできるため、新規顧客・既存顧客からの受注増・売上増を図ることもできます。
このようにBtoB-ECのシステムを活用することで、対面営業よりもスムーズかつ効率的に一定の品質の施策を実施することができ、自社のマーケティングを強化できることもBtoB-ECを導入する大きなメリットです。
顧客側にも多くの利点がある
BtoB-ECを導入すれば、導入側企業だけでなく顧客側企業にとっても次のような利点・メリットがあります。
取引をEC化することにより、インターネットにつながる環境さえあれば顧客は時間・場所に関わらず商品情報・在庫情報・納期といった取引情報を確認することができます。また、同時に受発注も簡単に行うことが可能です。
取引のプロセスもシンプル化されるため、顧客側も利便性向上や業務負荷軽減といったメリットを得ることができます。
BtoB-EC導入の際には、上記のような顧客側のメリットについての説明を行うと、取引先からの合意や協力も得やすいでしょう。
このようにBtoB-ECにはさまざまなメリットがあります。以下の記事でBtoB-ECシステムの詳しい検討ポイントについて解説しているため、併せてご参考下さい。
Web受発注システムの機能・導入メリットとは?選定のポイントも解説
BtoB ECの導入にデメリットはあるか

BtoB-ECの導入には、メリットだけでなくデメリットもあります。そのため、導入前にはリスクヘッジとしてデメリットが許容できる範囲内かを確認しておくことが非常に重要です。
ここでは、BtoB-EC導入に伴う主なデメリットについてご紹介します。導入を検討している方は、事前に確認しておくことをおすすめします。
導入コストが大きい
BtoB-ECの導入にあたっては、自社の取引形態や既存システムとの連携性に合わせた独自のシステムを開発・構築する必要があるため、導入コストが非常に大きいことがデメリットです。初期投資である導入コストが障壁となってBtoB-ECの導入が進まないという企業は多く見られます。
近年ではBtoB-EC専用のECパッケージやクラウドサービスも数多くリリースされているため、これらのカスタマイズで導入できる可能性もあります。フルスクラッチ開発よりも大幅なコストダウンを図ることができるため、導入コストが障壁となってBtoB-ECの導入が難しい場合は検討をおすすめします。
既存顧客への追加サポートが必要
BtoB-ECを導入する際には、従来の取引方法からデジタルへの大幅な変更が行われるため、既存顧客の合意や協力が必要不可欠です。場合によってはシステム導入後の取引方法の案内やレクチャーも必要となってくるでしょう。また、業界によっては業界の慣習や商習慣からの脱却が加わることがあるため、反発を招く場合もあります。このような状況のフォローについても考慮しておく必要があります。
このように、BtoB-ECは導入企業にも取引先企業にも大きなメリットがありますが、自社の意向だけでは導入できないことがデメリットです。自社本位に導入を進めてしまうとさまざまな問題が発生する可能性があることに留意しておきましょう。
BtoB ECを構築でおさえておくべきポイント
BtoB ECサイトの構築方法には様々ありますが、その特性故の機能がいくつかあります。必要な機能を備えたシステムを選びましょう。ここではBtoB企業特有のECサイトの機能についてご紹介します。
マスタ管理機能
BtoB-ECサイトでは従来の商取引で行われていた人を介した販売をEコマースに応用する傾向があります。故に企業の従来からあるシステムとの連携に重きをおくケースがBtoC-ECサイトよりも強い傾向にあると言われています。
そのため多くの場合、BtoB-ECサイトの商品管理はERPとの連携によって成り立っています。簡単に言えば、ERPにある商品データ・在庫データと連動させてECサイトの商品表示などに反映します。
例えば大手製造業の部品販売などにおいては数万点という規模の商品を扱うことの多いので、このようにマスタ管理を利用する必要があり、それがBtoB-ECサイトには求められます。
承認フロー
BtoC-Eコマースでは、決済権限のある自分自身が購入ボタンをクリックすれば購入することが可能です。しかし、企業では1案件あたりの単価が巨大になるケースもあるため個人で意思決定できるケースは多くありません。このようなケースを踏まえてBtoB向けのECサイトでは承認フローが自在に設定できる機能が備わっています。バイヤーに寄り添った機能だからこそ、顧客満足度を高めることができます。
見積管理
BtoB-ECサイトとBtoC-ECサイトの違いと言えば、見積があるかないかと言っても過言ではありません。企業の購買においては、見積書が不可欠です。バイヤーは見積をもらってから社内稟議を行い発注処理します。BtoC-ECと比較し、商品が高額な場合や、購入する商品や企業のレベルによってディスカウント料率が異なる場合があるので、購入前に見積もりを取得する必要があります。
一般的にバイヤー側には、自動見積と見積依頼という機能があり、バイヤーは必要に応じて企業の担当者に見積依頼を出すことも可能です。基本は自動見積によって見積書が作成されるので、作業効率アップにつながります。
管理者側の機能としては、見積依頼があった際は迅速な見積作成を行う必要があります。BtoB-ECサイトでは見積作成機能が備わっているので、スピーディに納期回答などを行えます。
受発注管理
受発注管理も、バイヤー側と管理者側に備わっている管理機能です。仮注文時に在庫の引き当てを行いサプライヤーや製造部門、配送部門へ通知し、与信管理システムと連動し与信金額超過していた場合は警告や注文不可とすることができます。もちろん、注文データの受付、チェック、注文確認メールの配信などにより、受発注ミスを無くすような機能も兼ね備えています。
また、BtoC-ECサイトではカード決済やコンビニ決済など個人を対象にした決済手法が一般的ですが、BtoB-ECサイトの場合には「月末締めの翌月末払い」など支払いサイトが異なります。それらを管理可能な売掛管理や請求管理機能などとの連携も必要になってくるでしょう。
ディスカウント
BtoB-ECサイトでは多くの場合、ディスカウントがあります。ボリュームディスカウントであったり、キャンペーンであたり、パートナーレベルに応じた料率出会ったり、実に様々です。これらのディスカウントを全て手動で管理することは難しく、手間も多くなります。また、バイヤーごとに適用するディスカウントが異なるので、管理はさらに複雑となります。
こうしたディスカウント管理も、BtoB-ECサイト特有の機能です。正しい割引適用額の提示により、信頼感を与えることはもちろんのこと、企業運営を円滑に行うことが可能になります。
バイヤー管理
バイヤー(代理店など)ごとに情報を管理することも必要不可欠になります。それぞれのバイヤーごとに割引料率や支払いサイト条件、締め日、支払い方法、最大購入金額などを管理し、マーケティングシステムと連携して、個別の販促活動に繋げることも可能です。このようにBtoB-ECサイトにおいて取引先ごとの管理を行うためのバイヤー管理は必要不可欠なものなのです。
まとめ
IT・インターネットの発展・普及により、多くの顧客の購買活動はデジタルにシフトしつつあり、企業間取引であるBtoBにおいても同様の傾向が見られます。今後BtoBビジネスを展開する企業が成長を続けるためには、BtoB-ECへの参入・デジタルシフトを行うことが重要となるでしょう。
弊社では、今後どのようにBtoB-ECを構築・導入すべきかという具体的な方法をまとめた資料を無料公開しています。BtoB-ECへの参入を考えている方や、BtoBビジネスのデジタルシフトを目指している方は、ぜひご活用下さい。
- カテゴリ:
- BtoB EC
- キーワード:
- BtoB ec